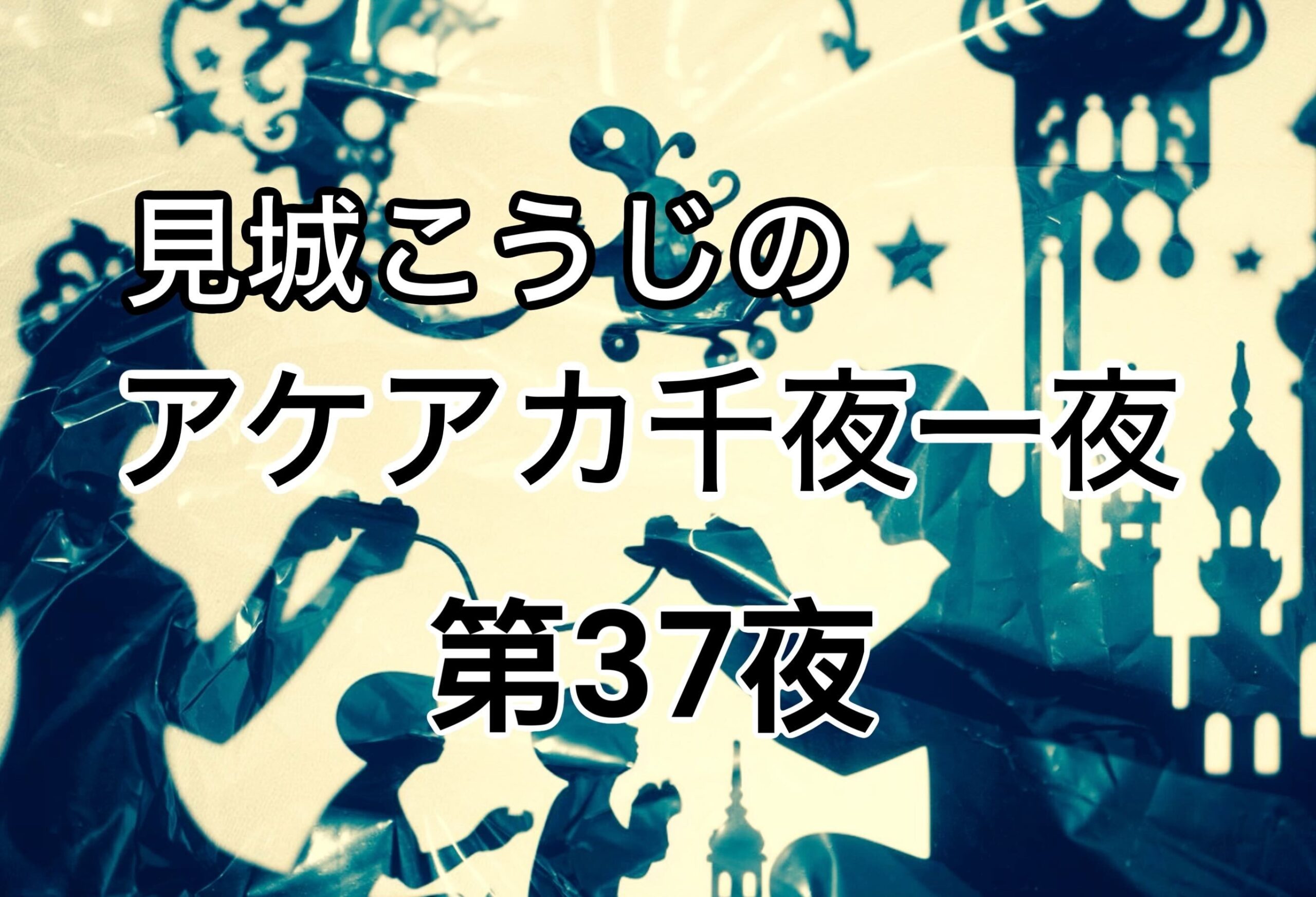見城こうじのアケアカ千夜一夜
第37夜『フロントライン』(1983年・タイトー)

『ワイルドウエスタン』に続くダイヤルスイッチシューティング
『フロントライン』は地上戦をテーマにしたミリタリー・シューティングゲームです。プレイヤーは歩兵から始まり、戦車に乗り込むなどして敵陣を進み、最後は敵司令部を手りゅう弾で破壊して1ステージクリアとなります。
同社『ワイルドウエスタン』同様、ダイヤルスイッチを採用していることが大きな特徴です
(両ゲームともアーケードアーカイブス版では右スティック+ボタンで近い操作が実現されています)。
ダイヤルスイッチは「回す」+「押し込む」機能を持った入力デバイスです。平たい突起のついたデザインになっていて、これを右手の親指と他の指で挟むようにして持ち、ひねって回すことで射撃方向を決め、押し込むことで弾を発射することができるというものです。
任天堂の『シェリフ』にも使われていたデバイスですが、前述のタイトーのゲームを経て、近い考えかたはSNKの『T・A・N・K』や『怒』等にも継承されました。
ダイヤルスイッチは、プレイヤーの移動と関係なく任意の方向に攻撃ができる画期的な操作法の一つでした。そこから生まれるゲーム性を考えると、のちのFPS系のオリジンの一つといってもよいかもしれません。
もちろん、これ以前にもツインスティック操作によってこれを実現した『ロボトロン2084』のようなゲームは存在していたのですが、日本では一時期、ダイヤルスイッチがツインスティックシューターの代替デバイスともいえる存在になっていました。

射程が短く接近戦が強いられるゲーム性
『ワイルドウエスタン』もそうですが、当時はまだ敵のバリエーションの概念が希薄で(ないわけではないのですが)、このゲームもほぼ兵士と戦車(小・大)しか登場しません。あとはトラップとして地雷が設置されていたり岩が転がってくるくらいです。
改めてプレイして感じたのは、プレイヤー、敵ともに射程が短いということです。
『フロントライン』はマニュアルスクロールで、プレイヤーの自由度が比較的高いことが一つの特徴ですが、敵がスピーディに攻めてくるようなゲームではありません。
そのため、自弾の射程が長いと遠くからチクチクと倒していくような戦法が成り立ってしまうので、おそらく難易度を作る上で射程を短くする必要があり、バランスを取るために敵の射程も短くなったのかもしれません。
あと、どちらかというと、前半の歩兵で戦うシーンのほうが緻密な遊びで、このゲームの売りである後半の戦車戦のほうがやや大味な(その代わり爽快な)ゲームになっているのもおもしろいと思いました。

戦車戦のリアリティ模索期のゲーム
素朴なグラフィックなので、当時はそこまで意識してなかったのですが、今見ると敵兵士のやられかたが生々しくて、ダーンッと吹き飛ばされ、天を仰ぐようにして死んでいきます。なかなかえげつないドット絵です。
また、敵兵士がやぶに飛び込む際のアニメーションや、やぶの中で下半身が隠れる演出も凝っています。
ただ、戦車のデザインや挙動は、必ずしもリアリティを重視したものではなかったかもしれません。現実の戦車の場合、基本的に前進・後退および旋回移動になるので、当時のアクションゲームの仕組みに当てはめると、なかなか遊びとして成立させるのが難しい。
結果として『フロントライン』の戦車はまん丸の不思議なデザインになっていて、8方向に自由に移動できる形になっています。
同じくタイトーの『スペースインベーダー』では当初、戦車戦のビジュアルをイメージしていたものの、それらしい動きが表現できなかったため、宇宙人にしたという有名な逸話があります。
そこから数年後のゲームである『フロントライン』では、兵士の挙動にしても戦車の動きにしても、(遊びとして別物とはいえ)『スペースインベーダー』でできなかったことをやっています。
それでも現代のゲームと比べれば、作りとして隔世の感がありますが、ゲームの進化の歴史を知る上で、とてもおもしろい作品だと思います。
では、また次回。

© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation