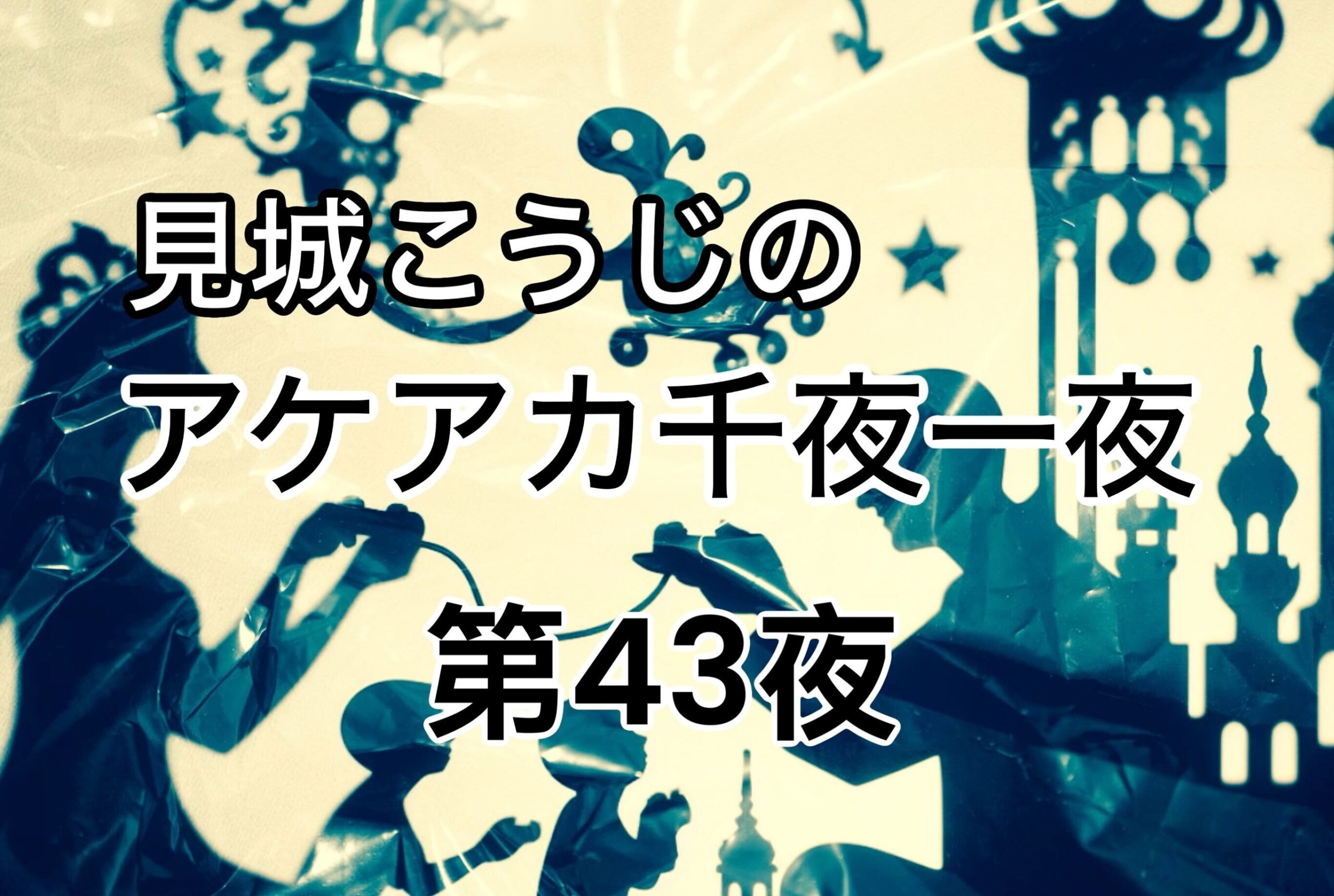見城こうじのアケアカ千夜一夜
第43夜『ラジカルラジアル』(1983年・ニチブツ)

主人公はタイヤ型の不思議なキャラクター!
『ラジカルラジアル』は、タイヤ型の自機を操作してゴールを目指すシューティングアクションゲームです。
操作は8方向レバーとショット&ジャンプの2ボタン。強制スクロール型ですが、レバー上下で自機の加減速が可能です。
ゲームは3つのエリアで1ステージとなっており、各エリアはシームレスにつながっています。
シューティング、レース風アクション、ボーナスステージの3面構成
最初のエリアは、障害物をかわしつつショットで敵を倒す高速スクロールのゲームです。途中で道が狭くなるなどの仕掛けもあります。
敵は1種類で、弾を撃ってくることはありません。体当たり攻撃のみです。基本は単独でバラバラに飛んでくるのですが、ときおり編隊を組んでくるので、これを全部撃ち落とすと1,000点のボーナスが加算されます。
なお、主人公は地上を疾走していますが、空中を飛来する敵にも弾が当たるタイプのゲームです。
2つ目のエリアは、打って変わって敵車とのレース風のゲームです。ここではショットは撃てなくなります。
道路にはオイルなどの障害物があり、登場する敵車は、大型車、小型車、後方から追い越してくる救急車風のもの、さらに前を走ってボーナスを落とすタイプなど、バリエーションに富んでいます。
余談ですが、当時あまりプレイしていなくてくわしいルールを覚えてなかったため、今回プレイし直した際に、データイーストの『バーニンラバ―』のようにジャンプで敵を上から押しつぶせるかと思ってしまいました(そんなことはできません)。
最後のエリアは、障害物をかわしつつターゲットを集めるボーナスステージです。すべてのターゲットを集めた際にはパーフェクトボーナスもあります。

同社『セクターゾーン』の前身的なゲーム?
改めてこのゲームを見て感じるのは、後年の同社『セクターゾーン』と遊びがよく似ているということです。カメラ位置こそ異なるものの、ゲームシステムも構成もそっくりです。
どちらもプレイヤー機が地表を高速で走り、スクロール速度の異なるシューティングメインのエリアと、障害物レースメインのエリアから成ります。
(ただ、『セクターゾーン』は障害物レース風のエリアのほうが高速スクロールだったので、そこは逆になっていますし、『セクターゾーン』にはボーナスステージがないという違いもあります)
加えて、どちらも世界設定にちょっとしたSFマインドが感じられる点でも似ているように思います。
少し脱線しますが、タイヤ型で道路を疾走する生命体というと、1965年に石原藤夫によって書かれた「ハイウェイ惑星」という有名なSF小説があります。
過去に滅びた文明が遺したハイウェイが惑星中に張り巡らされており、そこに適応した生物が高速で移動できるタイヤ型に進化していった、という発想で描かれた奇想天外な小説です(『ラジカルラジアル』の主人公が生命体なのかはよくわかりませんが)。
他にも乗り物という形であれば、いわゆるモノホイールは昔から長きにわたる開発の歴史があって、創作の世界でもたとえば手塚治虫の「ワンダースリー」にもモノホイールの乗り物が出てきます。
おそらく『ラジカルラジアル』の開発者も、このような過去のSF作品や実験的な乗り物を発想のベースにしたのではないでしょうか。

閑話休題。両ゲームを細かく比較していくと、ややシュールな世界観だった『ラジカルラジアル』に対して『セクターゾーン』には明確なバックストーリーがあり、ビジュアルや各種フィーチャーもそれに沿ったものになっています。
たとえば『ラジカルラジアル』では「100」「300」などの数字が書かれただけの、少々味気ない表現のボーナスターゲットだったのに対し、『セクターゾーン』ではペトラ人という具体的なキャラクターがボーナスターゲットになっていて、そこには「救出」というドラマ性が加わっています。
ぼくの想像に過ぎませんが、こうした類似点と進化した要素の数々を見るに、ニチブツにとって『セクターゾーン』は『ラジカルラジアル』のリニューアル版的な発想の製品だったのかもしれません。
では、また次回。

©HAMSTER Corporation
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation