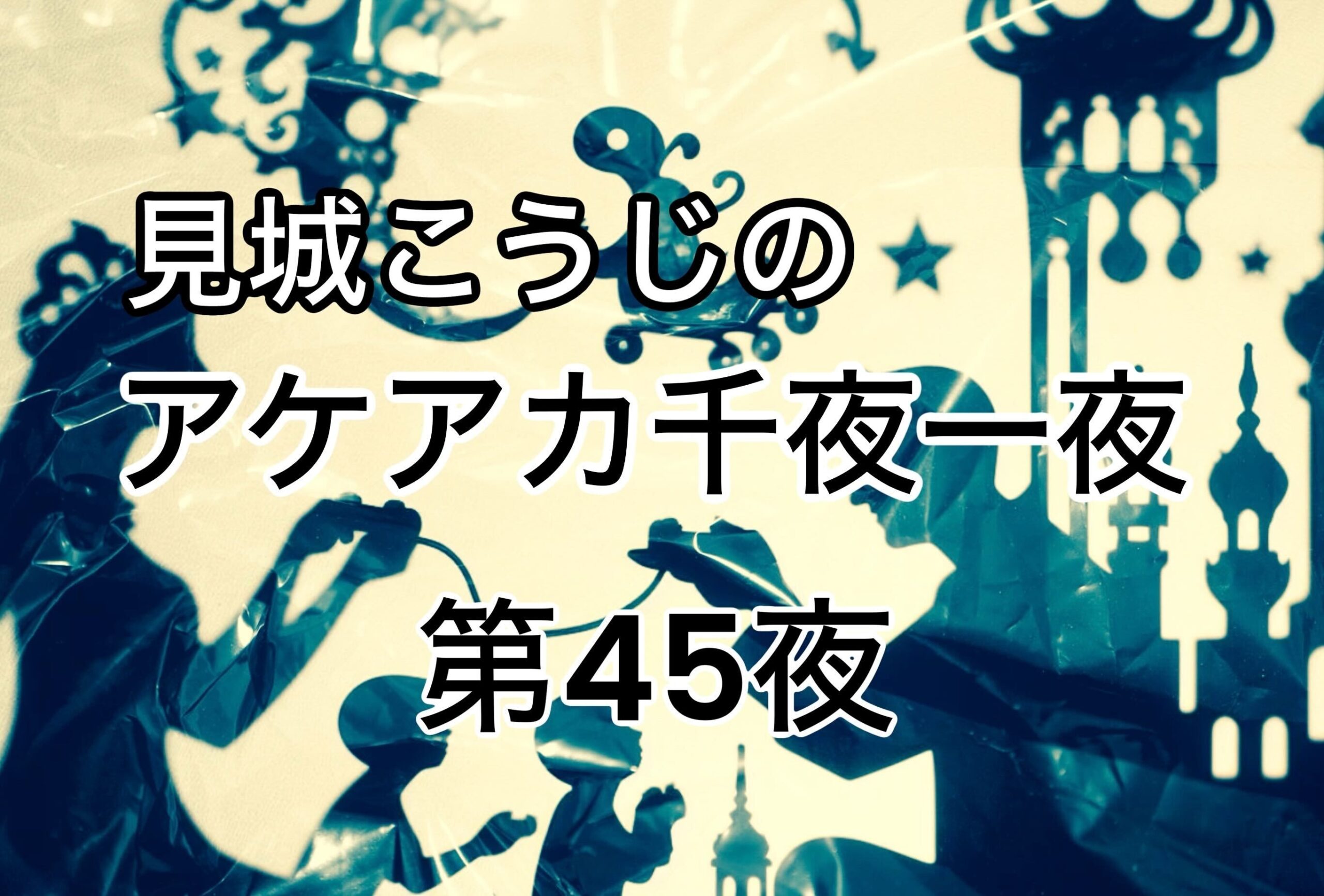見城こうじのアケアカ千夜一夜
第45夜『ワンダーモモ』(1987年・ナムコ)

ナムコの新たな時代に誘われてワンダーモモ華麗に活躍!
『ワンダーモモ』は、レバーとキック(兼変身)&ジャンプの2ボタンで主人公モモを操作して、悪の怪人軍団ワルデモンを倒していくゲームです。ゲームは4部構成で全16面(4面×4部)。バイタルゲージ制です。
当時はまだゲームで扱われることが珍しかった変身ヒロインが主人公であること、そして現実の戦闘ではなく、舞台劇の上演を行っているという設定が大きな特徴です。
敵を倒していくことでワンダーゲージが溜まり、一定量に達すると変身してパワーアップができます。特撮ものの聖地である採石場もしっかり出てくるなどオマージュ感もバッチリです。
当時、ぼくも1コインで最終ステージまでがんばって進めたのですが、ラスボスに勝てず心が折れてやめてしまった思い出があります。ラスボスのモズーと一緒に出てくる破壊不能の巨大タンクが強敵で……。

癖のある操作性に苦戦は必至! だが、そこがおもしろい?
当時も思いましたが、改めてプレイし直しても難しいゲームです。作りがあちこち独特なのです。
たとえば、ザコの戦闘員が地面の下から急に湧いて出てくるので不意を突かれたり、近寄ってくるときに妙に間の長いフェイントをかけてきたり。
それに対して主人公モモは一つ一つのモーションが大きく、かつやられ判定も大きいので、よくあるゲームの感覚でプレイすると対応が常に一歩遅れる。便利技の開脚キックなどもコマンド技のようなものなので、とっさに出すのはなかなか大変です。
ヒットチェックに関しては全体的にシビアな考えかたで作られていて、やられモーション中は変身アイテムのつむじ風に入れないとか、舞台の端にジャンプでぶつかるとダウン扱いになる等々、「そっちの処理を選んだかあ」と感じる箇所が散見されます。
ただ、慣れてくるとその独特の作りが癖にもなってきます。硬い敵に攻撃を当てたときの重量感のあるリアクションなどは、とてもよくできていると思います。
攻略に関しても、たとえば同じく硬い敵に対して飛び道具のワンダーリングを放った際に、遠くから当てるとリバウンドしたリングが大きく跳ねてしまいキャッチが難しくなるのですが、接近して当てると素早くキャッチでき、連撃を喰らわせやすくなるなどよく考えられています。

改めて注目したい“舞台劇”なる深読みしたくなる設定
制作者の言によると、ゲームをコンパクトにまとめるための苦肉の策だったそうですが、“舞台劇”という設定はこのゲームの中でもっとも独創的でおもしろいアイデアだったと思います。
幕が上がって上演開始する演出だったり、怪人に追われる子どもたちのセリフ「怖いよー」の昭和の子役っぽい棒読み感なども全部うまくハマっていますし、フラッシュをたいてモモを硬直させるカメラ小僧なんて、まさにこの設定ならではのギミックです。
その上で、これはぼくだけかもしれませんが、プレイしているうちに段々これは本当に舞台劇なのかよくわからなくなってきます。
というのも、たしかに背景にしても話の流れにしても舞台劇を表現しているのですが、ゲームをプレイしてみると、モモの跳躍力は明らかに人間を超えているし、リアルタイムに変身し、派手な光線技まで披露して敵を撃破しています(TVドラマという設定であればVFX等でどうにでもできるのですが)。
もしかしたら『ワンダーモモ』は舞台劇という体(てい)で、じつは本当のヒーローが地球の存亡を賭けて現実に戦っているメタな構造の世界なのかもしれません……なんてことを思ったりします。
当時はいろいろ物議をかもした『ワンダーモモ』ですが、ナムコの新時代を切り拓いた作品の一つであることは間違いないのではないでしょうか。
では、また次回。


WONDER MOMO™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation