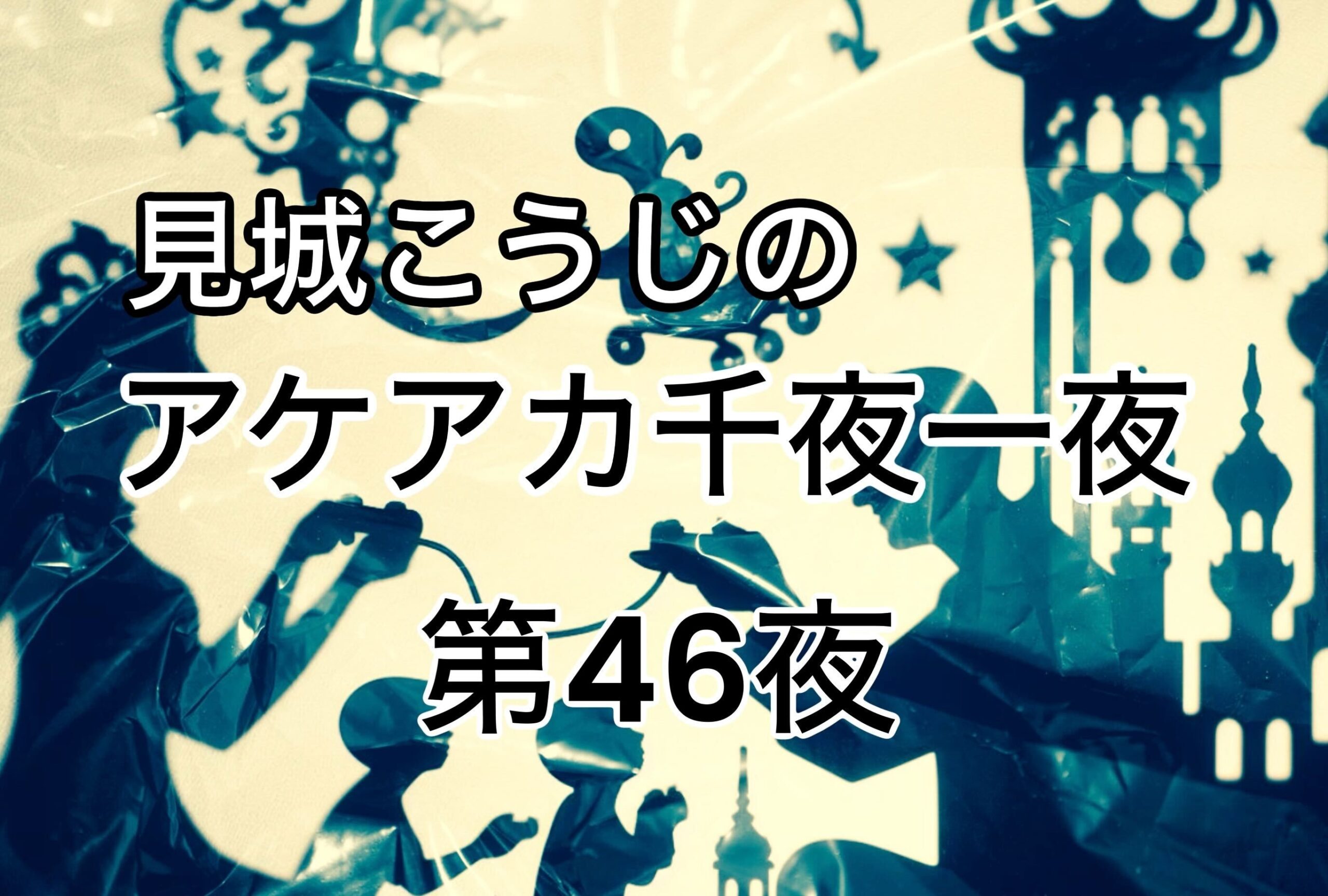見城こうじのアケアカ千夜一夜
第46夜『SENJYO』(1983年・テーカン)
今回の『SENJYO』は「アケアカ千夜一夜」初の2部構成でお送りします!
前半は通常どおり、ゲームのコラム、そして後半は当時テーカンで同ゲームの企画を担当された上田和敏さんと鶴田道孝さんへのショートインタビューをお届けします。

迫り来る敵タンクを撃破せよ! 3Dシューティング『SENJYO』
『SENJYO』(センジョウ)は、周囲360度から迫り来る敵と戦う3D視点のシューティングものです。
多重スクロールによって地形の凹凸が表現されており、丘の向こう側から敵が攻め込んでくる様子が演出されていたり、レーダーに映る敵影を確認して、そちらへ戦車の向きを変えるゲーム性など、コクピット筐体でも遊んでみたくなるゲームです。
敵は、メインのスペースタンクのほか、プレイヤーに向かって突っ込んでくるミサイルのようなバニッシュ、そして画面を横切り、破壊することでその後の得点倍率がアップするディテクターの3種類です。

じつは『スペースインベーダー』に似ている?
改めて遊んでみて、ゲームの構造としては『スペースインベーダー』によく似ていると感じました。
視点こそTPS風でまったく違うのですが、敵タンクはインベーダーよろしく左右に移動しながら徐々にプレイヤーに近づいてきて、プレイヤーはそれを単発のショットで確実に狙い撃って倒していきます。
UFOのごとく画面を横切るディテクターの撃破が高得点へのカギになっているところもよく似ています。さらに、敵の数が毎ラウンド固定ということと、全滅させることでクリアというルールも同じです。まさに換骨奪胎という感じがします。
視覚効果としては、先にも書いた複数のスクロール面による立体的な地形によって、進撃してくる敵が一瞬見えなくなるのがおもしろいですね。この地形の凹凸やレイアウトを、ラウンドごとにもっと大きく変化させたバージョンが見てみたいなあなんてことを思いました。
ディテクターのデザインが(性能が同じにもかかわらず)毎ステージ変わるのは、今の感覚だとちょっと違和感もあるのですが、『パックマン』のフルーツのようにボーナスターゲットがどんどん変化していくような感覚だったのかもしれませんね。
ちなみに指定のミッション達成によってスコアの倍率が上がるフィーチャーは、このゲームの企画者である上田和敏さんが『レディバグ』『ボンジャック』などでも採用している、いわばお家芸ともいえるシステムです。

レーダーなどの画面インフォメーションの特徴
難易度に関して思うのは、敵弾のホーミングが厳しいゲームだということです。
トップビューやサイドビューのシューティングの場合だと、プレイヤーに自由度があり、行動可能領域も広いので、無数の敵弾でじわじわ追い詰めていくようなゲームが多いのですが、『SENJYO』の場合、自機が一次元的な動きしかできないため、敵弾の一発一発が強く、少ない弾数で効果的にプレイヤーを仕留めにくる感じです。
また、近づいてくる敵を把握するにはレーダーを見たほうがいいのですが、改めてプレイしてみると、縦画面モニターの最下部に表示されているということもあって、視点を上下方向に移動させるのが大変でした。
ぼくは上手ではないので的確な考察かはわからないのですが、敵の接近を許さないようにするために、ゲーム中はスクリーン上寄りの遠方を中心に見ていることが多いので、それもあってレーダーを同時に見るのはなかなか大変なのかもしれません。
この辺も今ならレーダーを半透明にして、あまり邪魔にならない形でゲームフィールドに重ねることができるのですが、当時としては仕方なかったと思います。
それともう一点、改めて各仕様を見直していてちょっと驚いたのが、画面下部のインフォメーションの潔さです。出現する敵の総数が32で固定されています。このデザインにしてしまった以上、あとからバランス調整で敵の数を増やすことはできません。
この仕様の決め打ちはなかなか潔いと思いました(もちろん、それでも後付けで絵を変えずに32より多くしたい場合、何らかの方法はあると思いますが、わかりにくかったり、パッチ的な形になってしまいそうです)。
最後になりますが、『SENJYO』を現代の視点で見ると、アナログスティックで操作できたらなお楽しそうとか、自機のパワーアップ要素だったりグレネードランチャー的な武器がほしいなと思ってしまったりします。そう感じるのは、それだけこのジャンルのゲームが今なお進化を続けていることの証左かもしれません。
次ページからは開発者インタビューをお送りします!

©1983,1984 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation