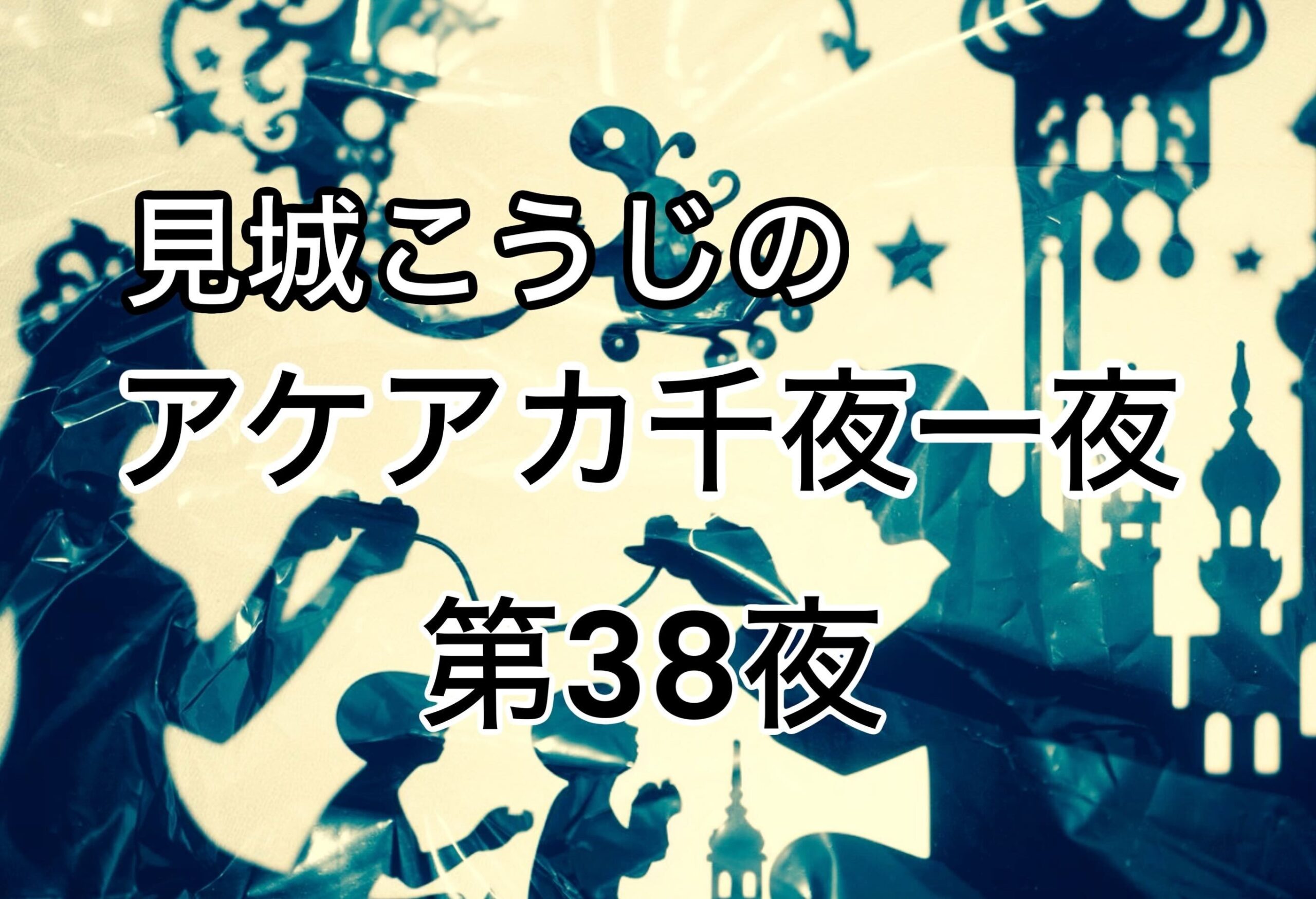見城こうじのアケアカ千夜一夜
第38夜『フェアリーランドストーリー』(1985年・タイトー)

2ステップで敵をやっつける固定画面アクションの秀作
『フェアリーランドストーリー』は魔法使いのトレミーを操作して敵を倒し、全101面をクリアしていく固定画面アクションゲームです。最終ラウンドに待ち受けるボス・ドラコリスクを退治することでエンディングを迎えます。ぼくも当時、全面クリアした大好きなゲームです。
トレミーは敵に魔法をかけてケーキにすることができます。さらにそこから連続で魔法をかけてやっつけるか、ケーキを押して下段に落としてつぶしてやっつけます。ケーキを落とした際に、下にいる他の敵も巻き込むことができます。
下から上へ通り抜けることのできるフロアや、2ステップで敵をやっつける仕組み等々、のちの『バブルボブル』『ドンドコドン』などのシリーズの原点に当たるゲームです。
新たなパズル性を生み出した画期的な移動システム
床を上方向にだけ突き抜けて移動できるゲームの元祖がこれなのか、ぼくにはわからないのですが、最初期の一つであることはたしかではないでしょうか。
これはかなり画期的なアイデアで、空間の使いかたにおいて“大胆な嘘”をついたという点で(=床のグラフィックで塞がれているのに、なぜか上方向にだけは進める)、シューティングゲーム『スターフォース』で、地上と空中の弾を共通にしたのにも近い気がします。
これ以前の多くのサイドビューゲームでは、上段へ昇るのは制約が大きく大変なことでした。ハシゴを使ったり、ジャンプするにしても床にぶつからないように横から飛び乗る必要があったわけです。
それが、このゲームは飛距離さえ届く範囲であれば、どこからでも床を突き抜けて上段へ昇ることができます。でも、下段に降りる際は床の切れ目や穴を使って降りるしかない。
『フェアリーランドストーリー』は、この移動の不可逆性のおかげで、マップの作りが独特なものになっています。
たとえばビジュアル的に閉鎖空間のような場所をはじめ、安易に上段へ進んでしまうとそこからの展開が厄介になるエリアを作ったりと、それまでになかった思考要素、新たなパズル性を生み出せるわけです。
パズル性の強さに関していうと、このゲームではラウンドによっては「プレイヤーがここに入ってしまうと詰み」という場所も設けられています。アーケードゲームとしては珍しい作りです。

敵をケーキにしてからが考えどころなのだ
ゲームとしては、敵をいかにまとめてやっつけるかというところが主眼になっています。1体をケーキにして、真下にいる敵の上に落とし、一網打尽にする。これが理想の形です。
それを実現する上で重要になってくるのが敵の誘導なのですが、これがけっこうやりやすいんですね。割と思ったように誘導できる。
たとえば、原則として他の敵はケーキを乗り越えてくることができないので、手前の一体をケーキ化すれば、そのまま奥の敵もろともグイグイと押していくことができます。魔法をかければ一発でケーキにできるということもあって、敵が近くにいてもそれほど怖くない(飛び道具を放ってくる敵もいるので、そこは注意が必要ですが)。
こうして見ていくと『フェアリーランドストーリー』は、岩の配置が固定だった『ディグダグ』から、プレイヤーが動かせるようにした『Mr.Do!』を経た、さらに発展形のゲームという見方もできると思います。
またもう一点、敵の誘導がしやすい理由として、トレミーが敵の頭の上に乗れる点も挙げられます。『ロードランナー』などにもある仕組みですが、これがあることで攻略の幅が広がっており、パズル性も高まっています。
それと、ちょっとしたことに見えるのですが、敵とケーキ間のヒットチェックがかなり小さめに取られていて、プレイヤーがケーキを押す際や、ケーキの脇を敵が落ちていく際に、多少敵がケーキに食い込んでもそのままゲームが進行します。こうした遊びやすくするためのヒット補正等のチューニングは、かなりしっかりしていると思います。
さらに、こうしたもろもろの遊びを実現する上でよくできているのが、トレミーの魔法射程の絶妙な短さです。これ以上射程が長いと、かえって遊びにくいかもしれません(同系統のゲームである『バブルボブル』では泡の射程を伸ばすアイテムがありましたが、取るとかえって遊びにくくなったことを思い出します)。
余談ですが、ケーキ越しに押された敵が踏ん張るアニメーションが可愛いんですよね。全体にキャラクターのドット絵がとてもキュートなゲームです。

強力なアイテムでガンガン進んでいく。それもまたよし
『フェアリーランドストーリー』で賛否がわかれるところだと思うのが、アイテムの出現法則です。
このゲームでは、敵を多く残した上で一定距離を歩くことで、強力な敵全滅系のアイテムが出現します。じつに多くのラウンドで、パズル的な解法を無視してあっけないくらい簡単にクリアすることができてしまう。これはいかがなものか?
……なんて書いたものの、ぼくも当時この強力なアイテムを出しまくって全面クリアしました。アイテムを使いまくると大味な遊びになると同時に、それはそれで爽快で楽しいのも事実なんです。
なかなかのバランスブレイカーな仕様であり、少なからずゲームを壊していることは間違いなく、この仕様がよかったのかどうかはよくわかりません。この強力なアイテムが存在しなかったら『フェアリーランドストーリー』の評価がどう変わっていたか興味深いです。制作者はどういうことを考えて、この仕様に落ち着いたのでしょうね。
最後にもう一つ。主人公のトレミーってラウンド開始時はほうきに乗って飛んでくるのに、幕間デモの長距離移動時はドラゴンに乗っているんですよね。長時間ほうきにまたがって移動するのは疲れるからなのか、それとも魔法力節約のためなのか。
では、また次回。

© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation