ビデオゲームミュージックの父 小尾一介氏×大野善寛氏ダブルインタビュー 前編
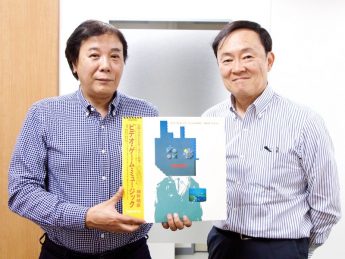
ゲームメーカーと音楽業界のかかわり
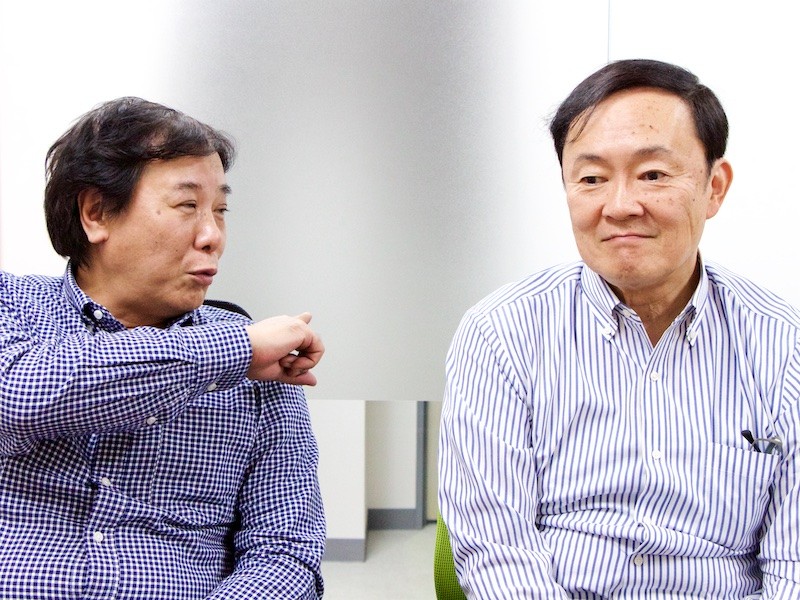
――アルファレコードは、一通りゲームメーカーさんのアルバムを出されましたよね。メーカーさんによってはVol.4までリリースして、その辺りは、1つのゲームメーカーさんがいけるんだったらほかもいけるだろうということになったのでしょうか。
小尾 これはこれでそれなりに売れたんですが、実は発売してからしばらくは動きがなかったんですよ。でも、¥ENレーベルには戸川純ちゃん(*01)とか、立花ハジメさん(*02)とかもいたし、一方ではスネークマンショー(*03)とかもやっていましたし。これは一つの企画アルバムっていう感じでスタートしましたが、その後はしばらく時間が空いたんです。
そして、1983年にファミコンというのが出てきた。そこで大野くんが僕に教えてくれたんです。「ファミコンっておもしろいですよ!」って。
――ここで大野さんが登場するわけですね。大野さんもその時はアルファレコードの社員だったんですよね。
大野 宣伝をやっていましたね、この頃は。
小尾 そうなの? 最初宣伝だったんだね。で、ファミコンっていうのがあって、『スーパーマリオブラザーズ』(1985年/任天堂)が大ヒットした。僕らが扱っていたのはビデオゲームだったけど、それがファミコンにどんどん移植されていきましたよね。
ファミコンは大ヒット、レコードもそこそこ売れてたんで、じゃあファミコンのレコードを出してみないかってことになったんです、アルファレコードとして。それで任天堂さんに行って、かくかくしかじかで『スーパーマリオ』をレコード化したいのですが、と。
当時『スーパーマリオ』は、ほかのレコード会社さんも出していた。「新婚さんいらっしゃい」の山瀬まみ。彼女なんて「『スーパーマリオ』のテーマソング歌います」なんて感じでデビューしたんですよ(*04)。当時の、ファミコンミュージックっていうものを作ろうっていう、1年半か2年くらい続いた流れの中で出したんですね。
――大野さんのファミコンミュージックがきっかけになっているわけですね。
大野 ファミコンは、僕はもう発売日に買いました。
小尾 「ファミコンミュージック」は、まあまあ売れました。でも、音楽業界とゲーム業界って、ほとんど接点がなかったんですよね。
――そうですよね。
小尾 ええ。ほとんど全部ビデオゲームメーカーでしたからね、あの頃は。ヒットした家庭用ゲーム機を発売していたのは任天堂さんくらいでしたよね。
だから、レコード会社の我々としては、宣伝・制作をレコード会社大手のビクターさんに委託していました。「今、ファミコンとかゲームがすごい流行っている」と、販路をお願いすべく「宣伝して」って(ビクターさんに)頼むわけですよ。
その後、僕たちが「このゲームミュージックを聴いた人たちがいっぱいいるから、これは必ず売れると思うんで頼みます!」みたいに、全国営業所にお願いして回りました。そうしたら「大ヒット」というほどもないですが、まあまあ売れたんですね。
これで味をしめて(笑)、「いろんなメーカーさんがあるから、いっそ全メーカー回っちゃおうぜ」みたいな話になって、それで始めたのが「G.M.O.レコード」っていうレーベルなんです。「¥ENレーベル」の中ではなくて、独立したゲームミュージック専門のレーベル。
今はもうあまりないんだけど、当時あったレコード店は、本棚みたいな棚にレコードを陳列していました。歌手名とかで五十音順にインデックスをつけてくれる。そこをちゃんと確保することって大事なんですよ。なぜかっていうと、新しいジャンルだから、レコード店がなかなか置いてくれなかった。
例えば、安室奈美恵さんとかのアーティストだったらすでに棚があるわけだけど、こういう企画ものっていろんなところに埋もれちゃうんです。
なのでそういう意味でも、まずは「ゲームミュージック」というジャンルを確立して、どこのレコード店に行っても棚がある、入れてもらえる場所が確保できているという状態、そこに目がけて「ここに置いてください!」って言える状態にしていかなければならなかった。
「ゲームミュージック」もしくは「G.M.O.」をレコード店に認識してもらうところから始まりました。
「クラシックとかポップス、映画音楽とか企画ものだってあるじゃないですか! だからゲームミュージックもどうですか!」と、そういう説得をしていました。「棚をください」っていう。
――私が最初に買ったゲームミュージックのアルバムが『セガ・ゲーム・ミュージックVOL.1』でしたが、店内のどこのジャンルにあるのか迷うんです。でも、それを探すのも楽しかったですね。
大野 当時、(ゲームミュージックのレコードは)はSL機関車やバイクの音などBGM・効果音のコーナーに置かれていることが多かった。
――そのうち、(ゲームミュージックは)アニメのコーナーとかに入れられるようになって。
小尾 映画音楽とかは、もうすでに昔からあるジャンルでしたし、どこのレコード屋さんに行ってもそういう棚はあるんです。だったらそれと同じじゃないかと。「ゲームミュージック」っていうのは一つの大きなジャンルだと思っていたし、(将来的に)そういうふうに持っていこうと思ってもいましたね。
――(小尾さんが)社内で最初に「G.M.O.レコードを作ろう」とおっしゃったとき、大反対を受けたとか、そういうことはありましたか?
小尾 いや、『ビデオ・ゲーム・ミュージック』もあったし、ファミコン自体が大ヒットして世の中に浸透していましたからね。たぶん、アルバムで言えばアルファレコードが最初に出したんじゃないかな…。
いち早く任天堂さんに交渉しに行って、「いいですよ」ってその頃に言われて。会社としてもそこそこ売れるんじゃないかという期待を持っていました。
――逆に(ビデオゲーム)メーカーさんの反応はどうですか。
小尾 メーカーさんのほうは、それこそ最初は「うーん」という感じだった。音楽業界は“文化”っていう歴史があって、レコードも一つのカルチャーとして確立しています。でも、ビデオゲーム業界というのは、当時、どっちかっていうと、それこそ縁日の釣り堀とか金魚釣りとかに例えられるような、そういう業界だと捉えられていました。
だからエンターテインメントという点では(音楽もビデオゲームも)一緒なんだけど、ビデオゲームを含むアミューズメントは、「文化である」という概念がまだなかったですね。
自分たちのやっていたことは今ふうに言えば、まさにコンテンツを作ってクリエイションしているわけなんですが、まだ一般には「文化」っていうふうには認識されていない。(ゲームミュージックも)流行って廃れていくものと思われていました。もしくは、ひょっとしたらパチンコに近いんじゃないか、とか。
ですから任天堂さんは、「レコードになる」って言ったら歓迎してくれたんです。社員の音楽家の人たちも、「自分たちの音がレコードという形で残るっていうのは、すごくうれしい」とね。
ビジネスとしてのゲームミュージック

――生々しい話ですけど、お金関係とかっていうのは…。例えば、許諾料をお支払いしてやるわけじゃないですか。その辺りのやりとりはいかがですか?
小尾 あんまりそういうの問題になったことないよね。
大野 はい。
小尾 逆に、「(レコードを) 出してくれてありがとう」みたいな。
大野 「(許諾料を)もらっちゃっていいんですか」みたいな(笑)。宣伝の一環にもなるし。
小尾 そうだね。
大野 窓口はだいたい販売促進部とかが多かったですね。
――雑誌での対談から細野さんと遠藤さんの流れがあって、「¥ENレーベル」でやりたいと。その時に、小尾さんと大野さんはどういったかかわり方をされていたんでしょうか?
小尾 最初は、僕が制作部で大野くんが宣伝部というかかわり方だったのかな?
大野 そうですね。媒体で紹介してもらうために、方々に重いレコードを運んで持っていくわけですよ。ラジオ局に持っていくと、どうしてもアーティストものが主体だから、まあほとんどが「はあ?」「ふーん」みたいな反応でしたよね。その中で唯一、反応が良かったのは、当時『ホットドッグ・プレス』(*05)にいたいとうせいこうさん。
――いとうせいこうさん!
大野 いとうせいこうさんは、そこのライターだったんですよ。
小尾 社員だったね。
大野 あの人は、もう「待っていました!」みたいなね。いろいろ聞いてきて、逆にこちらが「俺そんな詳しく分かんないんで」みたいなこともありました。
――お2人とも、制作と宣伝という側面で立ち会われた。
小尾 そう。あともう1人、近藤雅信(*06)くんっていう変わり者がいて、確か以前はユニバーサルの幹部だったのかな。「YMO」とともに人生を送ったみたいなおじさんがいるんですよ(笑)。レーベルの中で制作メンバーだった彼とよく一緒に仕事をしました。
――(近藤さんとは)その頃からガッチリとタッグを組んで。
大野 人数少ないんでね。タッグ組むどころか何でもやるんですよ(笑)。
小尾 大手だと何百人の中の30~40人(?)とかで作るんですけどね。
――ゲームのサウンドトラック(アルバム)自体、前例がないじゃないですか。どうやって作ったらいいか分からない、みたいなところはありましたか?
小尾 これは大野くんが詳しいと思うけど、基板から音を録るとかね。
大野 そうですね。
小尾 大変なんだよね。ノイズが入っちゃうんだよね。
――ナムコの大野木宣幸さん(*07)も加わったんでしょうか?
小尾 大野木さんは当時ナムコの社員で、ナムコさん側の音楽担当だったんですよね。ずいぶん助けてくれたと思う。基板を持ってきて、基板にマイク付けて音源を録音していました。専門家じゃないとおかしな反応になっちゃうわけでしょ。僕は現場をあまりよく見ていないですが、その辺はやりたい放題やったよね。
大野 そうでしたね。
――ライン録りとか?
大野 作曲者ですからね。ずいぶん試行錯誤されたんじゃないでしょうか。Aスタ(*08)入って基板動かして、その後どうすりゃいいの、みたいな。
小尾 最初はミノムシクリップ(*09)なんかでね、ボリュームのところから音を拾ってきてね。
次回予告
次回、中編では、いよいよサイトロンの制作秘話を中心に話を進めていく。もっとも売れたタイトルは何だったのか? いち早くデジタルメディアに目を光らせていた首脳陣が見たゲームミュージックの未来とは? 次週公開予定。乞うご期待!

小尾 一介 氏
「アルファレコード」「サイトロン・アンド・アート」を統べてきた、 ゲームミュージック業界の祖。その活躍は音楽だけに留まらず、マッキントッシュ用CD-ROMソフト「Shadow Brain」の開発・制作や、立体音響と3D映像ビデオソフト「ヴァーチャル・ドラッグ」シリーズの制作・販売など、枚挙に暇がない。現在は、ロケーションインテリジェンスを手掛けるクロスロケーションズ株式会社代表取締役を務める。

大野 善寛 氏
小尾一介氏と共に、1980年代以降のゲームミュージック業界を先導してきた第一人者。ほぼすべてのゲームメーカーと接点を持ち、ゲームと音楽ファンのために長く尽力してきた。現在は株式会社MAGES.(メージス)が運営する声優養成所「SAY YOU LAB(声優ラボ)」所長を務める。
脚注






