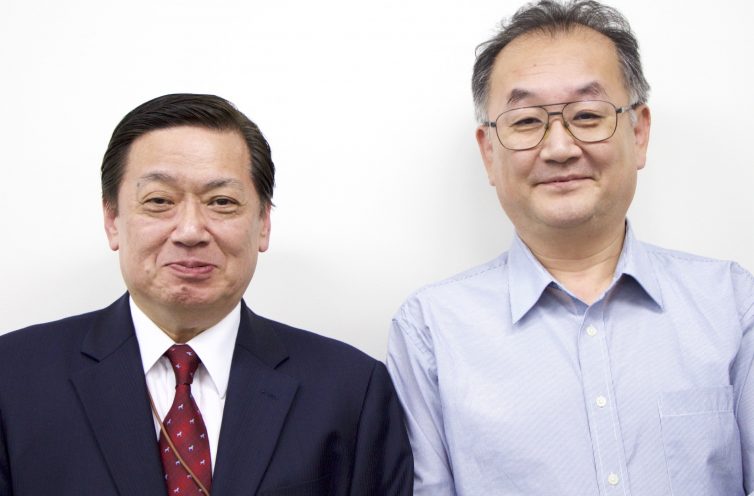伝説のゲームデザイナー・上田和敏氏×遠藤雅伸氏ダブルインタビュー 前編
1990年代に提出したオープンワールドの企画に「そんなものできない」

――もう一つ『Beep』での話題ですが、遠藤さんが「30人くらい一緒に遊べるゲームを作ってみたい」とおっしゃっています。この頃、通信ゲームはまだ珍しい時代でした。『ファイナルラップ』(1987年/ナムコ)も出ていない時期ですよね。開発はしていたでしょうけど。
遠藤 大体、僕は早すぎてダメなんだ。実際に実現できる頃に「よし一番だ」と言ってゲームを作ると、それが出てから2年後ぐらいに同様のものが流行る。
上田 僕もありますね。5年ぐらい後に来るという。
――アーケードで出たセガの『ラストサバイバー』(1989年)も、もう少し後ですね。
遠藤 ネットワーク自体がもう少し先でしょう。1990年代にならないとネットワークはきちんとしたものが出てこないし。
上田 iアプリ時代(*01)に『対戦ぐるじゃむ』(2001年/ジー・モード)では頑張りましたよ。一応、会員20万人。
――それはどういうジャンルだったのですか?
上田 基本的には1対1の対戦です。人と人との対戦はおもしろいだろうって、そういうのばっかり作りました。携帯電話で4人対戦は非常に難しい時代だったので、麻雀ゲームなども全部2人用に直して作りました。楽しかったですね。夜中でも皆さん遊んでくれたんで、明け方の4時頃でも対戦できるんですよ。それでユーザーさんから「(対戦しているのは)人じゃないだろう」と言われたこともありました(笑)。
――当時はそれぐらい新しい遊びだったんですね。

大堀 ゲームセンターみたいに営業時間とか関係ないですしね。家庭用で24時間遊べるようになって、ゲームがガラッと変わりましたよね。
――先ほどの遠藤さんの「30人くらい一緒に遊べるゲーム」というのは、ローカルではなく、遠方とのリンクを意識されていたんですか?
遠藤 『Habitat(ハビタット)』(1986年/ルーカスアーツ)をやっていた頃だったから、世界の国の人とゲームができればなあと。でも、レイテンシーが低すぎて話にならなかったし、無理でしたね。
1990年代に入ってからも、ドライブゲームでネットワークものが作りたいなと思って、島一つどこを走ってもいい『ドライブアイランド』というゲーム、今でいうオープンワールドを企画したことがあったな。運転手と助手席に乗っている人をネットワーク上で自由に組めて、視界がその位置で共有できて、いろいろな方向を向ける。運転している人はドライブゲームみたいな感覚でプレイできて、隣の人は周りを見ることができる。
いろんな走り方をする人がいるから、ゲーム側でそれを見るようにする。例えば、峠道で走行タイムを測れる機能がついていて、そこを走る人を500人ぐらいの人が見ている。シフトをどこでやっているか、どこでハンドルを切っているのか、ブレーキ早いなとか、その操作が運転席で見える、というようなゲーム。でも「そんなものできない、今の技術では無理」と言われた。
大堀 今ではそれに近いゲームが一般的になりましたね。
当時から立体テレビやホログラフィに憧れがあった

――上田さんは『Beep』で、「テレビモニターという方向性が変わらないと、代わり映えがしないんじゃないか、新しいものが作れないんじゃないか」「テレビ以外のものとか、立体テレビとかがあるといいなぁ」といったことをおっしゃっていますね。
上田 1978年頃、歌舞伎町のロケーションにテーブルゲームを持っていって設置しているときに、ふと「立体テレビが出るとゲームの世界が変わるだろうな」って思ったことがあったんですよ。たぶんそのことがずっと残っていて、その話になったと思うんですけどね。…ええと、名前、何でしたっけ? 新宿の大通りの角のゲームセンター。
大堀 スターダストですか?
上田 そう、そこにユニバーサルのインベーダーゲームをロケーションテストしてもらって、設置しているときに数台先のテーブルゲームの方をぼんやり見ていたら、立体テレビがイメージされたわけですよ。その頃はまだ3Dっぽいものがあっても3Dに見えないのが気に食わなくて、それでそんな話をしたんだと思います。まだ自分がゲームを開発する前ですね。
――ちょっと早いですよね。ニンテンドー3DSも何十年も先ですし。
上田 だいぶ後ですね。
――家庭用の立体テレビもここ数年のことですし。VRも最近になってようやく5万円とか2万円ぐらいでも手に入るようになりましたし。
遠藤 立体テレビはもうね、下に機械を置いて、映像がポーンと浮かび上がって…というのが、この頃からやりたかったな。
――ホログラフィですね。
大堀 アーケードで、セガの『ホロシアム』(1992年)というホログラフィーものがありましたよね。
――この頃、ゴーグルを付けてのVR的なものは、まだまだでしたね。
遠藤 あったことはあったけど、ポジションをとるのに、ゴーグル側に位置座標を読み取るセンサーが搭載できなかったから、当時はそれほど広まっていない。エリアが必要だったんだよね。ゴーグルの位置をほかのセンサーで感知しながらやっていたんで、ある程度のフィールドの中を歩き回ったりするVRがあった。今はゴーグルにセンサーがついているから、また変わっている。まあ、VR自体も、そもそもVRは何なのかという意識も、人によって違うよね。
――そこにいくと、めちゃくちゃ深い話になっちゃいそうです(笑)。
遠藤 どちらかというと、VRの話に限らず、新しいデバイスが出たときにそれを一番うまく消化して作ったゲームがやっばり時代を作っているね。
――何か具体例はありますか?

遠藤 一番分かりやすいのは、静電型のタッチパネル。それまでは圧力型だったから。しっかり押さなくてはいけなかったものが、スーッとなぞれるようになったときに、アメリカで『ダンジョンレイド』(2010年/Fireflame Games)という作品が出た。
――スマホのパズルゲームですね。
遠藤 そう。あれが出たときに、山本大介くん(*02)が「日本でおもしろいものを」って頑張って作ったのが『パズドラ(パズル&ドラゴンズ)』(2012年/ガンホー・オンライン・エンターテイメント)。『パズドラ』はうまく消化しているよね。マッチ3(*03)を一筆書きみたいにすることで、どんどんどんどん深いところまで行ける。
そこに日本のゲームの原点である「Easy to Start, Hard to Master」がある。これは世界的に言われる日本のゲームの素晴らしいところで、見ただけでどうやればいいかが分かりすぐに覚えられるけど、マスターしようとすると、そこには道があるという。
――『ダンジョンレイド』はかなり好きなゲームですね。数としては『パズドラ』のほうが圧倒的に出ているでしょうけれど。
遠藤 『パズドラ』のほうがおもしろいよ。『パズドラ』はスマホでクリクリクリって操作するじゃない? 最初はうまく動かせないんだけど、うまくなると「パァーッ」と派手になっていって、「うー、やった!」みたいなものがある。どこまで回せるかっていう。それが「hard to master」だよね。『ダンジョンレイド』はどこまでパネルを回せるかではなくて、最初にこれをこういうふうにしようと思うと、必ずそのようにできるじゃん。
――『ダンジョンレイド』はロジックのみですからね。アクション性はない。
遠藤 『パズドラ』には時間の概念があって、ある時間の中でどこまでできるかを、最初からイメージしながらやっていくところにおもしろさがある。それが簡単だというところがとても大事で、誰に遊んでもらえるかというデザイナーの考え方が『ダンジョンレイド』とは違うよね。山本大介くんはカミさんに遊んでほしいという気持ちから、あそこまで『パズドラ』の入口を低く設定している。ちゃんとゲームデザイン的におもしろいものを作ろうとして、それがおもしろくなるまで待ったというところは、ガンホーの社長の森下一喜さんの器量だよね。
次回予告
次回は1988年にアーケード版が発売された『テトリス』の衝撃。そして、『ポケモン GO』のプレイスタイルの違いから見えてくる日本とアメリカのゲーム観の相違など、現在、大学で教授を務める遠藤氏ならではのアカデミックなテーマにも言及していく。次週公開予定!

上田 和敏 氏
1954年生まれ。業界黎明期から活躍するゲームデザイナーの先駆け的存在。ユニバーサル勤務時代に『Ladybug(レディバグ)』(1981年)や『Mr.Do!(ミスタードゥ)』(1982年)、テーカン勤務時代に『スターフォース』(1984年)や『ボンジャック』(1984年)などの有名タイトルを手掛ける。その他、アトラス勤務時代に『女神転生』シリーズ(ナムコ、アトラス/1987年~)や『ダンジョンエクスプローラー』(1989年/ハドソン)、『キング オブ キングス』(1988年/ナムコ)など、アーケード、コンシューマー問わず多数の人気タイトルを企画。ジー・モード勤務時代には、モバイルにおいて新たなコンセプトを持った対戦ゲームサイトや『競馬ゲーム』など多数のカジュアルゲームにかかわる。現・サウザンドゲームズ取締役。

遠藤 雅伸 氏
ゲーム作家、ゲーム研究者。1981年にナムコに入社し、『ゼビウス』『ドルアーガの塔』などを手掛ける。現在は東京工芸大学芸術学部ゲーム学科教授、日本デジタルゲーム学会副会長、同学会研究委員会委員長などを務める。
脚注