西谷 亮インタビュー Part3

-
- 記事タイトル
- 西谷 亮インタビュー Part3
-
- 公開日
- 2020年01月25日
-
- 記事番号
- 2586
-
- ライター
- IGCCメディア編集部
対戦格闘ゲームの扉を開いた男 後編
ゲーマーから突然、ゲームクリエイターに転身し、直後から『ロストワールド』や『ファイナルファイト』などヒット作を連発した西谷 亮氏。その氏がつぎに手掛けたのが、対戦格闘ゲームの大ブームを巻き起こした『ストリートファイターII』であった。
ビデオゲームの歴史を変えたこの大傑作は、どのように作られたのか。
後編の今回は、その辺りを存分に語っていただいた。
「対戦格闘ゲームの扉を開いた男 前編」は、こちら。
「対戦格闘ゲームの扉を開いた男 中編」は、こちら。
【聞き手】
大堀康祐(ゲーム文化保存研究所 所長)
【聞き手・資料提供】
石黒憲一(娯楽産業研究家)
ずっとゲームを遊んできた自分を信じてます
―― 『ストリートファイター』シリーズでおもしろいのは、あんなにボタンがたくさんあるのに全部「攻撃」のためのものだという点です。
西谷 そうですね。その部分は崩さず、徹底してますね。
―― 個人的には大好きなのに、何だか操作がしっくりこないゲームに『ディフェンダー』(1980年/ウィリアムス)があります。ワープとかボムとか自機の向きを変えるとか、様々な機能がそれぞれのボタンに割り振られていて非常に夢のあるコンパネなのですが、いざ遊ぶとなると、なかなか思いどおりにいかなくて。
西谷 ああ、なるほど。わかりますわかります。ボタンを押し間違えても、『ストリートファイター』シリーズだと、とりあえず攻撃は出てくれますからね。
石黒 しかも『ディフェンダー』はタイトー版とニチブツ版とウィリアムス版で、すべてコンパネが違いますからね……。
西谷 私もあれは、自分が満足するほどは操作できなかったですね。


大堀 『ストII』を作るとき、初代を作った西山さんからアドバイスのようなものはなかったんですか?
西谷 そういうのは一切なかったと思います。というのも、さっきも言いましたが『ファイナルファイト』が終わったぐらいの段階で、岡本さんから「そろそろお前ら、自由にやってみろよ」と言われたこともあって、他から指示されたりアドバイスを受けたりというようなことはなく、本当に自由……というより、野放図にやらせてもらっていた感じですね。
大堀 あの岡本さんに、そこまで信頼されてたのはさすがだな……。
―― これも個人的に、なのですが一番驚いたのはガードが完全な防御だったことなんです。相手が通常技を出したとき、ガードしていれば一切ダメージを受けないじゃないですか。アーケードゲームだと、相手の技を完全に防御できてしまうとまずいんじゃないか……といったようなことは考えませんでしたか?
西谷 それは『R-TYPE』(1987年/アイレム)の影響かなと思います。
―― 「フォース」の存在、ですか?
西谷 まさしく、そのとおりです。私、『R-TYPE』を最初に見たとき、ものすごくビックリしたんですよ。壊れなくて弾も防御してくれて……みたいなフォースがあって、こんなのあったらゲーム終わんないじゃん!って(笑)。いや、実際は余裕で終わるんですけどね。でも、最初、本当にそう思ったんですよ。
大堀 わかるなぁ(笑)。

西谷 そういう体験があったので、『ストII』でも通常技では削れないかもしれないけど、必殺技はガードしても体力減るんだし……ずっと守りたい人は守っててください、と(笑)。ちょっとプレイヤーを驚かせたいな、なんて考えもありました。
石黒 ぼくが一番ビックリしたのは弱キックかな。
西谷 え、弱キックですか……?
石黒 空手とか実際の格闘技を見ていると、強キックみたいな技は出てくるじゃないですか。でも、ああいった格闘技の試合で弱キックは出ない(笑)。
西谷 あはははは(笑)、確かに!
石黒 弱キックって実際には真似できない技だけど、それをちゃんと表現している。そのことにすごい感動したんですよ。ゲームならではの技だ、って(笑)。
西谷 あれは、おそらく『ファイナルファイト』から来てるんでしょうね。あのゲームでは技を空振りすると、ものすごい勢いで連続で出ますよね。でも、開発初期は違って、空振りすると「……ぶん! ……ぶん!」と、技と技の間にそれなりの間があった。それが自分でプレイしていてすごく気持ち悪かったんですね。それで何とかできないかなぁって、ずっと考えていて。結局、デザイナーはちょっと嫌がっていたんですけど、技の途中をキャンセルして「ぶんぶん!」ってなるようにしよう、と。
―― なるほど。
西谷 そうしたら、技を空振りしているだけなのに、「おおっ、これ何か気持ちいいな!」となって(笑)。もちろん、しゃがみ強キックをぶんぶん出すわけにはいきませんけど、それなら弱キックぐらいは気持ちよく出せるようにしようと……そんなふうに考えて実装しましたね。
―― やっぱり「気持ちよさ」が重要なんですね。
西谷 自分で遊んだときの気持ちに嘘をついたらいけないと思うんですね。だから、長く遊べるゲームが好きなんですけど、気持ちよくないゲームは長く遊べても楽しくないというか、疲れちゃうじゃないですか。
―― ああ、なるほど! 同じことをくり返しと見られがちですが、やっぱりそこに「何か」ないと魅力に欠けるわけですね。
西谷 そうですね。
―― それでは、これまで遊んでこられた数え切れないゲームたちが西谷さんの感性を育てた、といった感じなのでしょうか。
西谷 それはありますね。いっぱいあると思います。『ハイドライドⅡ』のときも言いましたけど「根性値」とか(笑)。あとは……ヒットストップってありますよね。
―― 攻撃が当たったときに敵味方の両者が一瞬止まる演出ですよね。
西谷 そうです。『ファイナルファイト』でも使いましたけど、これを学んだのは『脱獄』(1988年/SNK)だったんです。あのゲームで、それを意図的に入れていたのかはわからないのですが、とび蹴りをしたときにちょっと引っかかるような感覚があって。プレイしたときに、あ、これだ!と(笑)。
石黒 『脱獄』は海外でやたらとインカムがよかったそうですね。外国の人も、同じように何かある、って感じてたのかもしれませんね。
西谷 そういえばカプコンでも、わざわざ海外から基板を取り寄せて「これ遊んでおいて」って言われた記憶があります。

―― 西谷さんの原点は、ご自身で遊んだときの感覚だと。
西谷 そうです。そこは長年、ずっとゲームを遊んできた自分を信じてます。殴ったときの音とか、殴られたほうがズズッとずり下がるときの感じとか。そういうところには、とにかく強くこだわってきています。
―― その辺のこだわりは、理論的な裏づけのようなものはあるんでしょうか?
西谷 私は結構、理屈で考えるタイプかな、と自分では思っています。そのせいもあって、先にこれぐらいのパンチの尺ならこれぐらいのダメージが妥当だろうとか、最初はそうやって作るんですけど、それだけだとやっぱりうまくいかない。堅い感じのゲームになってしまうんですよ。ですから、そこで路線変更して、まずは気持ちよさを優先して調整してみよう……となりますね。そういうのが、何だか私のルーチンになっているような感じもあります。
―― デジタルだけじゃなく、アナログな感覚も大事だと。
西谷 それはすごくあります。特にアーケードゲームだと気持ちいいとか、何か引き込まれるものがないと次の100円玉を入れてもらえないじゃないですか。自分がゲーマーだったこともあって、その辺りはすごくシビアに考えてますね。他でも言ってますけど、『ストII』の(ダメージを受けたときの)ずり下がりの軌道なども最初は加減速の式を使ってちゃんと計算していたんです。でも、それだけだと何だか気持ちよくない。なので最終的には私が方眼紙にドット絵を描きながら考えて、これがいいんじゃないかなという、そういったやり方に切り替えました。
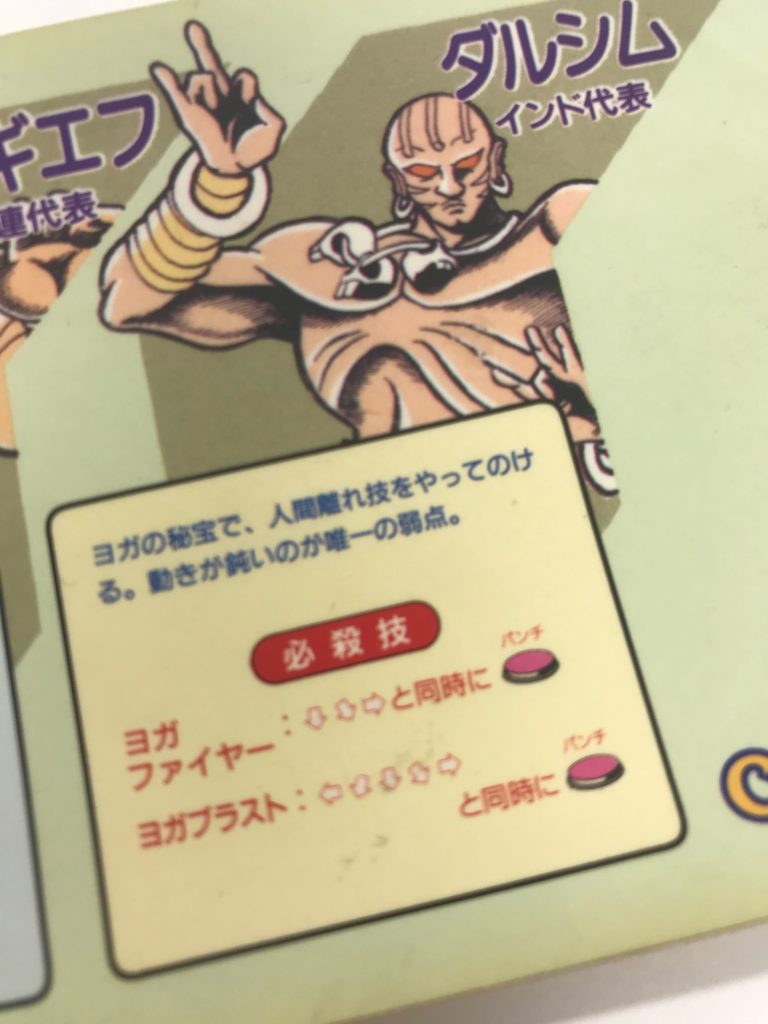
―― つぎにお聞きしたいのは「対戦」についてです。対戦におけるバランスというものについて、どのようにお考えですか?
西谷 当時の話ですけど、バランス調整は一生懸命に頑張るけど……これは無理だ、と思ってましたね(笑)。やっぱり組み合わせの数が非常に多いのに、あの頃はチームの人数もそれほど多くなかったので、完璧に調整するのは不可能だなぁと。でも、丸くするのは嫌だなとも思っていました。
―― 丸くする、というのは?
西谷 尖った部分があったほうがおもしろい、ということですね。なので、尖った部分は残しつつも、極端な差は生まれにくいような感じで調整したつもりです。
―― 大昔の対戦というと、将棋とかチェスとか、同じ性能のコマを同じ数持っているといった感じの「対象性」が大事で、だからこそどちらが強いのかハッキリさせることができたんだと思います。そういった勝負の世界に『ストII』のような「非対称性」を持ち込むことに不安などはありませんでしたか?
西谷 バラエティに富んでいることのほうが大切かな、と当時は考えていたと思います。バランスを取るのは極論すると簡単で、全部同じ性能のキャラにしちゃえばいい(笑)。でも、それだとまったくおもしろくないですし。
大堀 今考えても、ホントに『ストII』の登場は衝撃的だったよね。ジャンルを作ったゲームだし。あれでビデオゲームの歴史が変わったと思うよ。
『ストII』が数々のライバルを生み、そして育てた
石黒 そういえばテストモードって、どうして外部に漏れたんですか?
西谷 テストモードというと、キャラの当たり判定とかが画面上に出るアレですか?
石黒 そうです。『ストII』はゲーム自体もすごくおもしろいんですけど、このテストモードの存在も大きくて。あれを見て、多くのゲーム開発者が「格闘ゲームがどういうものかわかった」とか「格闘ゲームをどう作ればいいのかわかった」と言ってたんですね。
西谷 ああ、それは私も言われましたよ(笑)。ものすごく勉強になりました!って。それで私もよかったなぁって。
石黒 え、よかったんですか?
西谷 だって、それでゲーム業界のレベルが少しでも上がったんだとしたら、すごくいいことじゃないですか。
石黒 太っ腹だ……。

―― そうしているうちに、雨後のタケノコのように対戦格闘ゲームがそれこそ数え切れないほどリリースされることになります。その中で、西谷さんが「これはやられた!」と思うようなゲームはありましたか?
西谷 ありましたね。私、はじめて『サムライスピリッツ』(1993年/SNK)を見たとき、衝撃を受けましたよ。たとえばグラフィックで、こういう感じもあるんだとか。ゲーム面においても『ストII』以上に各キャラがもっともっと差別化されていたりとか。
―― 武器がある、というのも目新しかったですね。
西谷 そうなんです。同じ対戦格闘というくくりでも、ゲーム性は全然違う。強斬りでザキュッと斬りつけるときの気持ちよさとか。とにかくいろいろと新鮮で、ああ、こういった方向性もありなんだと、目の前がパッと開けたような感じがしました。
大堀 そういえば、昔、西谷さんと『ストII』の話をしていたときに聞いたんだけど。『サムライスピリッツ』が出たとき、「ああ、カプコンは終わったな……」って言ってましたよね。
西谷 そうそう。覚えてます。私、あのとき岡本さんに「このままだと完全に負けますよ」って言ったんですよ。
―― そこまで危機感があったんですか。
西谷 ええ。ホントにビックリしたんですよ。

―― 他のタイトルはどうですか?
西谷 カプコンのタイトルになってしまいますけど『ヴァンパイア』(1994年/カプコン)もビックリしたゲームですね。特にあの絵。あそこまでやるか!と。
―― 『ヴァンパイア』だと、開発の途中経過もご覧になっていたんですか?
西谷 ええ、ちょこちょこ見せてもらってました。最初のデザインだけでも相当長い間、方向性を定めるために様々な試みをしていたんですね。デザインだけでも半年以上、試行錯誤が続けられていたような記憶があります。あとはガード状態をキャンセルして攻撃に転じられるとか。

―― その辺りの企画面について、他のタイトルのかたとお話をしたりは……。
西谷 もちろん、いろいろとしましたね。特に当時はとにかくインカムを上げるためにはどうしたらいいのか。ぶっちゃけ、1秒でも2秒でもいいからどこかを削りたい。そんなふうに私を含めて企画の人間は考えていたんです。
―― 1秒でも2秒でも……。
西谷 格闘ゲームの場合、どこが削れるのか。いろいろ話していて、これはもう「ガードの時間」を削るしかないかな、と。そこから生まれたのがガードキャンセルだったというふうに、私は認識しています。
―― うまくなるとプレイ時間が短くなるというのはいいですね。
西谷 レースゲームと一緒ですよね。遊んでいるほうも達成感があり、なおかつインカムも上がる。Win-Winです(笑)。
大堀 あの当時って、大人だけじゃなく子どもも格闘ゲームにコインをばかすか入れてたよね。達成感と悔しさと。そういうものが入り混じった感情に支配されて。
―― 老若男女問わずに、みんな夢中になってましたね。
大堀 インカムがいいゲームで俺が思い出すのは、『怒』(1986年/SNK)とか『怒号層圏』(1986年/SNK)なんだけど、あれって二人同時プレイで友だちの手榴弾でも死んだりして(笑)。そういうとき、むかついてついついコンティニューしてた(笑)。でも『ストII』って、結構みんな納得してコインを入れていたような気がする。負けてすごい悔しいけど、心のどこかで納得してる。それがすごいなって。
西谷 そう言っていただけると頑張った甲斐がありました(笑)。

―― 『ストII』はグラフィックも美しいだけではなく、当時としてはパターン数も多く、じつにスムーズにキャラが動いていたと思います。あの多彩なキャラというのは、企画である西谷さんが美術チームにどれぐらい指示していたんですか?
西谷 安田さんたちと一緒に設定はいろいろ考えましたね。ラフをたくさん描いていただいて。でもある程度の方向性が決まったら、わりと自由にデザイナーさんに描いてもらうような感じで進めましたね。
―― エドモンド本田のステージで銭湯のお風呂場がありますが。
西谷 あれですね……背景担当の子が、ああいう案を出してきちゃった。こ、これは何だかすごいぞ、と(笑)。
―― NGは出さなかったんですか?
西谷 出さなかったですね。あ、ちょっと豆情報があるんですけど。あの担当の人って女の子なんですけど、最近会って話を聞いたら、あれ以降はお風呂の出てくるステージは彼女が全部描いているって言っていました(笑)。
―― お風呂専門!
西谷 そうなんですよ。
―― 『ストII』はカッコいいには振らずに、どちらかというと「笑いはすべてに優先する」という雰囲気すら感じますが……。
西谷 それはありますね。打ち合わせをしていても、笑いを取ったら勝ち!みたいな雰囲気は確実にありました。
―― 打ち合わせに勝ったり負けたりがあるんですか……。
西谷 ブランカもそうですね。ああいった風貌なんですけど、最初は肌色だったんですね。で、それをみんなで見ながら、「うーん、何かおもしろくないなぁ」と。それであれこれいじってみた結果、緑色の肌のブランカが上がってきて、「何だこれは! これいいよ、これ!」と(笑)。それで決まってしまうという。そういうことが積み重なっていって、全員がとにかくおもしろいものを追求していくようになったんでしょうね。
―― 関西のノリなんでしょうね。
西谷 そういう意味では『ザ・キング・オブ・ファイターズ』(1994年/SNK)とは真逆の位置にいるゲームかもしれませんね。あっちは、みんなカッコいいじゃないですか。それに全員、町にいそうだし。でも『ストII』のキャラは、絶対どこにもいない感じがする(笑)。
―― 町には……確かにいなさそうですね。
大堀 ブランカとか、いたら怖いし!
西谷 そういえば、『ストII』のぬいぐるみがありますけど、あるスタッフが中国に視察に行ったとき、現地の人に「春麗みたいな人はいないのか」と訊いたら、「いるわけないだろ!」と怒鳴られたとか聞きましたね(笑)。
大堀 やっぱり中国でも本物の春麗はいないかぁ……。

続編嫌いの西谷氏が、なぜ『ストII’』を手掛けたのか
―― 話は変わりますが。西谷さんは続編をあまり作りたがらないそうですが、『ストリードファイターII’』は手掛けられていますよね?
西谷 私、すごい飽きやすい体質なので……。でも『ストII’』は……続編というつもりはなかったんですよね。
―― と言いますと?
西谷 私は、ぶっちゃけ納期を守らない男で(笑)。それなのに企画マンの性として、いつまでもゲームをいじって(調整して)いたいという……。『ストII』も納期をオーバーしてもあれこれいじっていたんですけど、さすがにもう出さないとマズいということで発売することになったわけです。
―― なるほど。
西谷 で、次のゲームのプロジェクトがスタートするまでに少し時間があるということで、私とメインプログラマーの子で、勝手にいろいろ調整したりしてたんですね。
大堀 趣味で!?
西谷 まあ、そういうことになりますね(笑)。そんなことをしていたら、発売した『ストII』が非常に好調だと。それでちょっとバージョンアップしたものを出してもいいよ、みたいなことになって。それで、おおっ、これは渡りに船だ、と。
―― その調整バージョンが『ストII’』になったわけですね。
西谷 ただ……今でこそソフトのバージョンアップなんて、ネットワークもあるので当たり前のようにやっていますけど、当時はじつは少し罪悪感があったんですね。
―― 罪悪感ですか?
西谷 ちょっと技を変えただけの基板を発売するのって、何だかいろんな人に悪いような気がしてしまって……。そういう気持ちもあって、どうせ出すなら、もっといろいろ変えたほうが喜ばれるに決まってる、と。
―― それで四天王を追加するなど……。
西谷 そうなんですよ。今、思うと大胆なことしてますよね(笑)。で、そんなことしてるから、また時間がなくなって(笑)。そもそも四天王とか、操作する前提で技とかを考えているわけじゃないので大変でしたね。
―― 『ストリートファイターII’ターボ』には関わらなかったんですか?
西谷 『ターボ』は関わってませんね。でも最初、その話を聞いたとき、私は反対したんですよ。
―― え、そうなんですか!?
西谷 速くなったら絶対にゲーム性が変わっちゃうから、やめたほうがいいって主張してたんです。でも、実際に遊べるようになってプレイしてみると、あのスピード感が刺激的で「うぉー、何これ! すっげー楽しいっ!」って(笑)。
―― いきなり変わりましたか!
西谷 そのあと『ストII』に戻ってみると、「何じゃこれは、遅すぎて全然おもしろくないぞ! やっぱターボだな!」と(笑)。
大堀 西谷さん態度変わりすぎ!
西谷 いやぁ、プレイヤーとしてそこは正直にならないと(笑)。

―― 続いてスーパーファミコン版の『ストリートファイターII』についてもお伺いしたいのですが……こちら、西谷さんも関わっているんですよね?
西谷 そうですね、やってます。
―― となると、西谷さん初めてのコンシューマゲームということに?
西谷 あ……ああ、確かに言われてみれば、そうですね。気が付かなかった(笑)。
―― なぜコンシューマ版に関わることになったのでしょうか?
西谷 当時は、すでにアーケードと家庭用で部署が完全に分かれていたんです。なので、普通なら関わることはないんですけど、さすがに『ストII』はカプコンとしても大きなタイトルだということで、岡本さんに「これは、ちょっと手伝ったほうがいいよ」と言われて、それで手掛けることになりましたね。移植作とはいっても、変なものが世の中に出たりするのがすごく嫌だったので……。
―― 西谷さんは先ほど(このインタビューの「前編」で)「当時、アーケードゲームからの移植とは名ばかりのゲームが蔓延していたじゃないですか。あれが許せなくて許せなくて(笑)」とおっしゃっていましたよね。
西谷 そうですね。だから手伝うことに異論はありませんでした。どうせやるなら、とことんまでやろうと。ハードが違うので、まったく同じとはならないでしょうけど、プレイ感覚をとにかく近づけようと考えましたね。
―― どのあたりが一番苦労しましたか?
西谷 まず処理速度が足りませんでしたね。だから走査線、何本か分を切ったんじゃなかったかな。
―― それは画面の上下を少し切った、ということですか?
西谷 そうです。だからアーケード版に比べて画面が少し横長になってるんです。あと大変だったのは……やっぱり容量でしょうね。アーケード版にあるキャラのドット絵を全部入れることはできなかったので。
―― 似ている攻撃がひとつの絵になっていたりしましたね。
西谷 ええ。このキャラの弱キックと中キックは似てるから、同じグラフィックにまとめてしまおうとか。そういう涙ぐましい努力を重ねて、ちょっとずつ容量を稼いでいったんですよ。でも、絵は同じでも当たり判定まで同じだとそれはまったく同じ技だなと思って、それはどうしても嫌だった。だから、見た目とはちょっと異なるけど、攻撃判定を違和感ない程度に変えたりしてます。
―― かなりこだわって作られたんですね。
西谷 家庭用チームとがっつり頑張りましたよ。
―― 容量が足りずにご苦労されたとのことですが、最後、ベガを倒すとちゃんと各キャラ固有のグラフィックなどでエンディングが用意されていますよね?
西谷 やっぱり、あれは入れないとダメですもんね。
―― ぼく、じつはスーファミ版の攻略本を作った関係で、サンプルロムの段階から遊ばせていただいていたんですけど、最初はエンディングで固有のグラフィックが入っていなかったんです。
西谷 ああ、そうでしたっけ。ゲーム部分以外はほとんど関わっていないので、そこは見てないなぁ。たとえば、どんな感じになってるんですか?
―― たとえばブランカだと、お母さんと再会して、「あ、そのアンクレットは!」という感じで、足にはまっているアンクレットをさっと見せるシーンがありますよね。
西谷 はい、ありますね。
―― あのとき、ブランカの立ち弱キックを使ってたり。
西谷 あははは、似てる! 確かに似てる(爆笑)!
―― あと、最後、ブランカがお母さんと抱き合うシーンは、ブランカの噛みつき攻撃のグラフィックが流用されていて……。
西谷 あははは、それいい(笑)! それ見たいなぁ。何とか似ているグラフィックパターンを探してきて、それでエンディングを組んだんですね。
―― ただ完成版のロムでは、ちゃんと一枚絵に差し替えられていて……。
西谷 さすがに、このままはマズいってことになったんだと思います。でも、そのバージョンが隠しとかで入ってたら楽しいですよね。
大堀 それにしてもあのスーファミ版、よく出来てたよね。
石黒 スーファミ版とか『ストII’』の家庭用がすごい売れたので、町のおもちゃ屋さんまでが等身大の春麗のPOPを置くようになったんですよね。
西谷 それ、カプコンが送ってきたものですよね。
石黒 そうです。本当は今日、持ってこようと思ったんですけど、雨が降ってたから……。
西谷 え、持ってるんですか(笑)!
石黒 あれでこれまでは『ストII’ターボ』だったのが『ストIIターボ』になったんですね。
西谷 そうですね、POPにもそう書いてありましたし。

ヒーローなんやからすごいで!
―― 続いて、『X-MEN チルドレン オブ ジ アトム』についてですが。こちらのタイトルは、なぜ西谷さんが手掛けることに?
西谷 これは……何度も言ってますけど、私はかなりの飽き性で、同じのを作るのは嫌だと。
―― それでも、こちらもジャンル的には同じ「対戦格闘ゲーム」ですよね。
西谷 岡本さんに、こう言われたんですよ。「『ストIII』と『ヒーローもの』、どっちがいい?」って。『ストIII』は作りたくなかったんですね。自分がやるよりも、ほかの人が担当したほうが違う味が出るでしょうし。そっちのほうがプレイヤーにとってもいいことなんじゃないか、と思えたんです。で、じゃあヒーローものって何だろうと岡本さんに訊いてみたら、「ヒーローなんやからすごいで! 飛んだり跳ねたりビーム出したり、すごいいろんなことができるんや。どうや?」と(笑)。そんなこと言われたら、やってみたくなるじゃないですか(笑)。それで担当することになりました。今、冷静になってみると「ああ、同じ対戦格闘だなぁ」と思いますけどね。
石黒 それにしてもマーヴル(現在は「マーベル」が公式となっていますが、当時の表記に準じてここでは「マーヴル」といたします。ご了承ください)のIPを使えるって、とんでもないことですよね。
西谷 そうですね。
―― マーヴルはやっぱり厳しいですか?
西谷 ですね。でも、気持ちもわかるんですよ。勉強のために、いくつかマーヴルのIPを使ったゲームを遊んでみたんですけど、「こいつ、こんなことしないだろ!」みたいなのがすごく多い。元のイメージとかけ離れすぎたものになってしまうと、双方にとっていいことではないな、と。なので、厳しいことを言われるのも仕方がないかなとも思いましたね。
石黒 ヒーロー同士を戦わせたりして大丈夫だったんですか? 戦えばどちらかが勝ち、もう一方が負けて……ということは、ヒーローの負けパターンを作らなくちゃいけないことになりますよね。
西谷 それは『ストII』の実績のようなものを信用してくれたのかもしれませんね。直接、そう聞いたわけじゃないので想像ですけど。

―― ゲーム内容などは、マーヴルのかたに頻繁にチェックされるんですか?
西谷 たびたび来ていただきましたね。最初は「こいつらに任せて平気なのかな」みたいな懐疑的な雰囲気をびしびし感じましたけど、途中から変わっていって、「ああ、こいつらなら任せても大丈夫そうだな」みたいに思ってもらえたようです。だからこそ続編の『マーヴル・スーパーヒーローズ』(1995年/カプコン)とか、『VS.ストリートファイター』シリーズにつながってくれたんでしょうね。
―― あのマーヴルの信用を勝ち取ったというのはすごいことですよね。
西谷 あ、でも一度、岡本さんと私とでニューヨークに土下座しに行ったことはありますけどね(笑)。
大堀 何かやらかしましたか(笑)。
西谷 ちょこちょこ怒られたことはありましたけど、中でも一番怒られたのは……センチネルでしょうね。原作だと光線だとかむやみに撃たないじゃないですか、ただの人型ロボットという感じで……。でも、それだと地味だしゲームにならないので、光線撃ちまくったりいろいろすごいことさせたら……。
大堀 すごいこと(笑)。
西谷 これが、どうも先方の逆鱗に触れたようで(笑)。「センチネルは日本のアニメのロボットのように、むちゃくちゃなことはしない!」と。なので、これはもう土下座しに行くしかない、と(笑)。
―― え、それってリリース前……ですよね?
西谷 そうなんですよ。なのに、そこまで激怒するかな、と(笑)。
―― まあ、でもそれだけ自社のIPに対して深い愛情があるってことなんでしょうね。
西谷 どうなんですかね(笑)。そもそも、一番最初はウルヴァリン以外は1P、2Pの色替えキャラを出すことさえも拒否されてたほどですからね。
―― それは厳しい!
石黒 1Pと2Pの色替えの同キャラの概念って、『ストII’』から一般化したと思うんですけど、どこから来たものなんですか?
西谷 あの色も適当にやっているんじゃなく、それなりの意味があるんです。当時、すでに海外のプレイヤー文化とか嗜好とか、そういった知見を得ていて、「ああ、この人たちは、ちょっと変えたぐらいじゃ全然気づかないんだ」と(笑)。
―― まるっきり変えないとわかってもらえない?
西谷 そうなんです。もちろん、ずっと遊んでもらえればわかってもらえるんですけど、ゲームセンターでちょっと見ただけだと、細かい部分に気も留めない。
―― つまり、ダイナミックに変えることが第一の目的だったと。
西谷 そうです。インパクト重視ですね。
―― 話を『X-MEN』に戻しますが、他にマーヴルって厳しいなぁと感じたところはありましたか?
西谷 そういえば思い出しましたけど、『パニッシャー』(1993年/カプコン)にキングピンっていう裏社会を仕切ってるボスが出てくるじゃないですか。ゲームだからすごく大きく作ってあるんですけど、あれも「キングピンはただの人間なので、こんなに大きいのはあり得ない!」って死ぬほど怒られてたんです。それなのに、この前(2019年)公開された「スパイダーマン: スパイダーバース」って映画に、馬鹿デカいキングピンが出てきていて、「何だよ『パニッシャー』に出てくるキングピンよりもデカいじゃん!」って思いましたけど(笑)。
―― そこまで厳しいのに、よく豪鬼を入れるのを許してくれましたよね。
西谷 勝手に入れましたからね……。何かこういうのを入れたほうが絶対におもしろいよなぁと思って。
大堀 マジで(爆笑)? 勝手に入れたの? 見つかって怒られなかったんですか?
西谷 どうですかね(笑)。私は怒られなかったですけど……でも、これをやったことで半ば公認みたいな感じになって、それで『X-MEN VS. ストリートファイター』につながったんじゃないかなって勝手に解釈してるんですけど。

―― 『X-MEN チルドレン オブ ジ アトム』というと、「ベクトル理論」という概念を導入したことでも知られていますが。
西谷 そうですね。当時はそんな言葉、なかったかもしれませんが、「物理演算」みたいなことをやったらおもしろいんじゃないかと、ずっと考えていたんです。ちょうど『X-MEN』なら人間を超越した部分が多く、これならできるかなと思って……。
―― なるほど。
西谷 床体操って競技がありますよね。あれっていくつかの基本的な動きの組み合わせでおおよそは表現できると思うんですけど、あんな感じでいくつかの動きの要素を組み合わせて技を作る、みたいなことを本当はやってみたかったんです。そこにはちょっと届かなかったかもしれませんけど、それでもある程度はおもしろいことができたんじゃないかなとは思ってます。
次回予告
「後編」はここまでですが、まだまだ西谷氏には語っていただきたいことがあります。
カプコンをお辞めになって、アリカを設立したこと。満を持してリリースした『ファイティングEXレイヤー』について。そして未来のこと……。
次回は「特別編」と題して、こういったことをお聞きしていきます。
どうぞ、ご期待ください。

西谷 亮
1967年東京生まれ。
1986年株式会社カプコン入社。
業務用ビデオゲームソフトの企画職として『ストリートファイターII』『ストリートファイターII’』の開発に携わる。
カプコン在籍時には、『ロストワールド』『ファイナルファイト』『X-MEN』などの企画も担当。
1995年株式会社カプコンを退社。
同年株式会社アリカを設立、代表取締役社長に就任。 代表作は『ストリートファイターEX』シリーズ、『EVER BLUE』シリーズなど。






