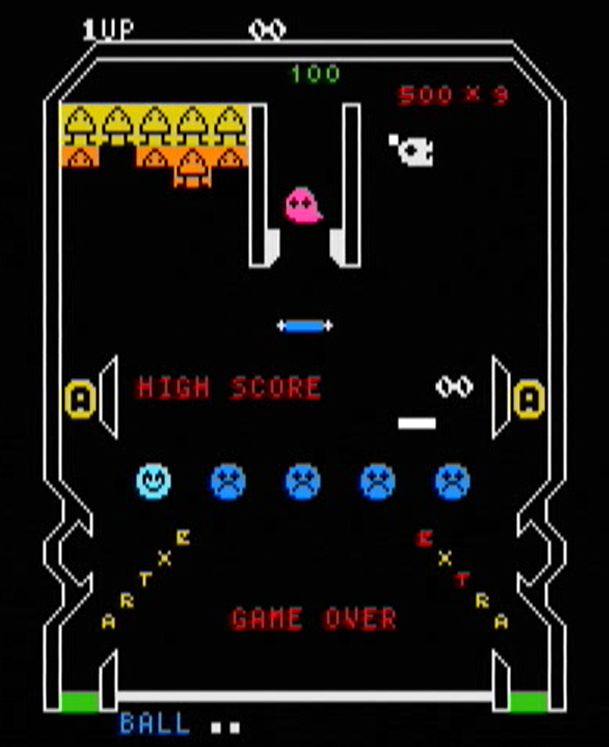「ゲームニクス」で考えるゲームの魅力 第十回 デモ画面
当コラムでは、「ゲームニクス理論」をもとに、なぜゲームがおもしろくなるのか、どうしてプレイヤーはゲームに夢中になってしまうのかを、おもしろおかしくご紹介していきます。
第十回目のテーマは、これまでとはちょっと趣向を変えて、プレイヤーが操作をしていない間の演出、すなわち「デモ画面」を取り上げてみたいと思います。
アーケードゲームにおいて、とりわけビデオゲーム黎明期は、通り掛かった人にアドバタイズ(宣伝)として「デモ画面」を見せることでいかに興味を引き、同時にゲームのルールを理解させてインカム(売上)を稼げるのかが極めて重要なポイントでした。筐体に貼られたインストカードにもルールはもちろん書いてありますが、実際のゲーム画面を見たほうが理解しやすいのは明白ですよね。
誰かが遊んでいる様子を見ることで、そのゲームのルールを覚える方法ももちろんありますが、ゲームセンターの営業中にプレイヤーが常時遊んでいるとは限らず、また専門のインストラクターが店舗にいるとは限りません。ですから、アーケードゲームにはアドバタイズの役割を果たす「デモ画面」は欠かせない要素なのです。
以下、先人たちがいかに「デモ画面」に工夫を凝らしていたのか、改めて振り返ってみたいと思います。
「ゲームニクス」とは?
現亜細亜大学教授のサイトウ・アキヒロ先生提唱による、プレイヤーが思わずゲームに夢中になる仕組みを理論・体型化したもの。
本稿では、「ゲームニクス理論」を参考に、ありとあらゆるゲームのオモシロネタをご紹介していきます。「理論」というおカタイ言葉とは正反対に、中身はとってもユルユルですので、仕事や勉強の休憩時間や車内での暇つぶしなど、ちょっとした息抜きにぜひご一読を!
基本ルールをわかりやすく伝える「スコアテーブル」の演出
初期のアーケードゲームの「デモ画面」は、1面あるいは数面分のプレイデモを順番に流し、通り掛かった人にどうやって遊ぶゲームなのか、短時間で理解してもらえるように意図して作られていたように思います。
さらにプレイデモに加え、独自のおもしろさをアピールするために登場キャラクターを紹介する画面を用意したり、どの敵を倒したら何点獲得できるのかを示した、いわゆるスコアテーブルをデモ中に盛り込むタイトルが非常に目立っていました。
また、『スペースインベーダー』(タイトー/1978年)のスコアテーブルには、敵のUFOの得点を「?(MYSTERY)」と表示し、具体的に何点入るのかを隠す演出があります。
謎めいた演出をすることで、プレイヤーに「おやっ?」と思わせて興味を引くとともに、プレイ中にUFOが出現したら、「破壊したらいったい何点もらえるのかな? ヨシ、じゃあ狙ってみるか!」というモチベーションにつながる、見事な演出になっています。
このように、高得点や隠しアイテムなどがもらえるフィーチャーを「?」などの表現であえて伏せておき、プレイヤーの興味、あるいは想像力をかき立てる「デモ画面」のアイデアは、同じくタイトーの『ちゃっくんぽっぷ』(タイトー/1984年)や、『スクランブル』(コナミ/1981年)などのタイトルにも取り入れられています。

やがて時代が進むにつれて、ゲームのジャンルやタイトル数がどんどん増え、ルールや操作方法が多様・複雑化していくと、ゲーム内容を徹底的にレクチャーする「デモ画面」が登場するようになっていきます。
そのわかりやすい例のひとつが、『バブルボブル』(タイトー/1987年)でしょう。
本作では、通常ステージの「デモ画面」とは別に、日本語の説明文を添えた基本ルールを教えるデモも流すことで、本作を初めて見た人でもゲーム内容を容易に理解することができます。
「デモ画面」に限らず、昔のビデオゲームの大半はテキストは英語(アルファベット)で、日本語で表示されるタイトルは極めて少数派でした(※インストカードはもちろん日本語で書かれていますが)。
これは当時のコンピューターに日本語のフォントが標準で搭載されていなかったのが原因と思われますが、幼い頃の筆者はなぜゲーム画面も日本語で表示しないのか、不思議でしかたがありませんでした。
ですが、本作に関しては、ほかの人がプレイしているのを見ただけでは遊び方がよくわからなかったものの、日本語の説明文を交えて丁寧に作られたデモ画面のおかげでルールがわかり、とても助かった記憶があります。
とりわけ、日本語のテキストを添える形で基本ルールをレクチャーする「デモ画面」が定番になっていたのは、『テトリス』(セガ/1988年)に端を発する落ち物パズルゲームではないでしょうか?
『テトリス』以外にも、『コラムス』(セガ/1990年)、『ぷよぷよ』(セガ/1992年 )、『コズモ・ギャング・ザ・パズル』(ナムコ/1992年)など、日本語による解説付きの「デモ画面」が用意された落ちものパズルゲームは、枚挙にいとまがないほど多数存在します。
さらに『エメラルディア』(ナムコ/1993年)では、1人プレイで誰かが遊んでいる最中にも、空いたスペースを利用してチュートリアルの「デモ画面」を流し続けるという珍しい、かつおもしろいアイデアが導入されていました。
もうひとつ、「デモ画面」の進化と開発スタッフのこだわりぶりがよくわかる例をご紹介しましょう。
以下の写真は、『ラリーX』(ナムコ/1980年)と、その続編にあたる『ニューラリーX』(ナムコ/1981年)です。
前者は遊び方を英語のテキストだけで表示しているのに対し、後者はキャラクターの絵とその役割を併記することで、より目を引きやすく、かつわかりやすくなっていることがわかります。
『ニューラリーX』は前作よりもキャラクターが増え、よりおもしろくなったことをアピールするために、開発スタッフが「デモ画面」にも改良を加えたのは至極当然だったことでしょう。
当時から、「デモ画面」の演出がいかに重要視されていたのか、非常によくわかる例ではないかと筆者は思います。
思わず注目してしまう、「デモ画面」の秀逸な演出
ここからは、単に基本ルールを紹介するだけでなく、「デモ画面」を利用していかにプレイヤーの興味を引き、100円玉を投入する動機につなげる工夫をしていたのか、さまざまなアイデアの実践例を見ていきましょう。
見た目にも非常にわかりやすい「デモ画面」の演出としては、派手な場面をひたすら見せ続け、ビジュアルのインパクトでプレイヤーの目を引く方法がまず挙げられます。
例えば、『グラディウス』(コナミ/1985年)や『TATSUJIN(達人)』(タイトー 開発:東亜プラン/1988年)、『ダライアスII』(タイトー/1989年)などのシューティングゲームでは、自機がフル装備になった状態でショットを撃ちまくるデモプレイを見せることで、プレイヤーに大きなインパクトを与えていました。
もしこれらのタイトルの「デモ画面」が、自機が初期装備のままだったとしたら、果たしてプレイヤーの興味を引くことができたでしょうか?
初期装備とフル装備とでは、そのインパクトには雲泥の差があることは明らかでしょう。
また、『スイマー』(テーカン/1982年)や『達人王』(タイトー 開発:東亜プラン/1992年)などのように、画面を覆いつくさんばかりの巨大な敵、またはボスキャラが登場するシーンを「デモ画面」に用意して、プレイヤーに強烈なインパクトを与えたタイトルもいろいろありました。
しかし、敵のインパクトが強過ぎるあまり、「こんな強そうな敵は、俺の腕では倒せないよ……」とプレイヤーを委縮させてしまうデメリットもあったかもしれません。

同じく、シューティングゲームの『エグゼドエグゼス』(カプコン/1985年)にも、おもしろい「デモ画面」の演出があります。
本作には、「POW」アイテムを取ると敵がフーズ(得点アイテム)に変化するユニークなアイデが導入されているのですが、「デモ画面」でもこのおもしろさをプレイヤーにアピールすべく、「POW」を取る場面を盛り込んでいます。
しかも、デモプレイ中にはいわゆるザコ敵だけでなく、いかにも強そうな敵の大型昆虫もわざわざ登場させたうえで、画面内の敵が一瞬にしてフーズになってしまう瞬間を見せてくれるので、実に強烈なインパクトがありました。
本作における「デモ画面」の演出は、当連載の第三回のテーマで取り上げた、「逆転の発想」によるおもしろさを見せる手法としても非常に優れていると思います。
そして「デモ画面」を語るうえで、とりわけ絶対に忘れてはいけないと筆者が考えるアイデアが、実は前掲の『スペースインベーダー』に導入されていました。
本作のスコアテーブルを表示するデモは2種類あり、2番目のデモではPLAYの「Y」の文字が上下逆さまに表示されるのですが、これはけっしてバグや誤植などではありません。
2番目のスコアテーブルが表示された直後、何と敵のインベーダーが現れて「Y」を正しい文字に直すという、とてもユニークな演出が盛り込まれているのです。
筆者は以前、幸運にも開発者の西角友宏氏にインタビューする機会に恵まれました。
取材中、「デモ画面」の話題になった際に西角氏は「よくあれを自分で思い付いて入れたなって。あそこはちょっと自分ながら、今離れて見てね、感心してますよね」などと仰っていました。
(※西角氏のコメントは、平成27年度「ゲーム産業生成におけるイノベーションの分野横断的なオーラル・ヒストリー事業」にて実施した、「西角友宏第4回インタビュー後半:コンシューマーゲームの開発と未来のゲームへの展望」より一部抜粋して引用しました )
※参考リンク
一橋大学イノベーション研究センター
プレイヤーから見れば倒すべき存在であるインベーダーを、コミカルな演出の「デモ画面」にも利用して通り掛かった人の目を引くアイデアは、ビデオゲーム史上に残る偉業ではないかと筆者は思います。
ちなみに、この誤字を直す演出は『いっき』(サン電子/1985年)の「デモ画面」にも登場します。
本作の開発スタッフに直接確認を取ってはいないのですが、『スペースインベーダー』の「デモ画面」にインスパイアされた可能性が非常に高いように思われます。
本作を発売当時にプレイした経験がある人であれば、ゲーム内容とともに独創的な「デモ画面」の演出もきっとご記憶のことでしょう。
ちょっと変わった「デモ画面」の演出をしているのが、『ギャプラス』(ナムコ/1984年)と『ドラゴンスピリット』(ナムコ/1987年)の両シューティンゲームです。
『ギャプラス』は、特定の敵を倒すともらえるパーツを、『ドラゴンスピリット』ではアイテムを持った敵を倒すとランダムで出現するハートマークのアイテムを、それぞれ3個集めるごとに自機のストックが増えるようになっています。
どちらのタイトルも、ゲームオーバーになった時点でストックしていたパーツ、およびハートは、次に遊んだプレイヤーにそのまま持ち越されるようになっています。
しかも、持ち越しとなったパーツやハートは、「デモ画面」の最中にもあえて表示し続けるのです。
つまり 「デモ画面」を通じて「今遊ぶとおトクですよ!」とアピールしているわけですね。
筆者も当時、ゲーセンに出掛けたときにパーツやハートが残っていたら「今日はツイてるなあ!」と、嬉々として100円玉を投入した経験があります(苦笑)。
お笑いネタを盛り込み、「デモ画面」をおもしろくする例も少数ながらあります。
前述の『いっき』や、『超絶倫人ベラボーマン』(ナムコ/1988年)では、何と登場キャラクターがカメラ目線で、こちらに向かって「プレイしてくれ」とアピールする演出があり、プレイヤーの目を楽しませてくれます。
近年の「デモ画面」の工夫例
ここまでは、古い時代のタイトルばかりをご紹介しましたが、近年のアーケードゲームにおける、「デモ画面」のおもしろい例もざっとご紹介していきましょう。
大型の専用筐体を活かした、アーケードゲームならではの秀逸な「デモ画面」の演出のひとつに、戦車を操る対戦アクションゲームの『TANK!TANK!TANK!』(バンダイナムコゲームス/2009年)があります。
本作の筐体には、プレイヤーの顔を撮影するためのカメラが搭載されていますが、「デモ画面」の最中はカメラでとらえた映像をモニターに表示するようにしています。
「デモ画面」でもあえてカメラを起動させることで、通り掛かった人の歩く姿が画面に映し出され、道行く人が「あれっ?」と思わず振り向いてしまうという仕掛けです。
また、レースゲームの『ロードファイターズ』(コナミ/2010年)は、3Dメガネを使った立体映像が楽しめるのが特徴で、「デモ画面」の最中はシートの背もたれにある「のぞき穴」から画面を見ることで、着席せずに3D映像を気軽にのぞき見することができます。
こちらも実におもしろいアイデアですね。
※参考リンク
『TANK!TANK!TANK!』
『ロードファイターズ』
2000年代以降は、「デモ画面」だけを見せるライブモニター、あるいはターミナル筐体を用意したタイトルが目立つようになったのも大きな特徴のひとつでしょう。
『麻雀格闘倶楽部』(コナミ/2020年)や『MJ Arcade』(セガ/2017年)の両麻雀ゲームがその一例で、プレイヤーの対局リプレイや、ゲームに参戦する実在のプロ雀士の打ち筋を見て楽しむことができます。
また後者の場合は、ネットワークを介して他店舗でのリプレイ(※主に役満などの大きな手をあがった場面)が流れることもあります。
ゲームをひと目見て興味を持った人が、お金を払わなくても気軽にゲームを体験できるよう、「デモ画面」も操作して遊べるようにしたタイトルもいろいろあります。
最新のタイトルから例を挙げますと、選手カードを使って遊ぶ野球ゲームの『BASEBALL COLLECTION』(コナミ/2019年)、クイズゲームの『クイズマジックアカデミー 輝望の刻』(コナミ/2020年)や、『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック アーケードゲーム』(セガ/2020年)などがあります。
以下、余談になりますが、デモ中に操作できるゲームの歴史は意外と古く、『影の伝説』(タイトー/1985年)には1面と4面の「デモ画面」のみプレイできるアイデアがすでに導入されていました。
ただし、「デモ画面」が操作できることを画面内にもインストカードにも表示しなかったため、気が付く人が非常に少なかったように思います。
また、本作のニューバージョンでは「デモ画面」の操作が一切できなくなってしまいました。
これは旧バージョンにおいて、4面の「デモ画面」を操作してクリアすると、画面が止まってしまうというバグがあったためではないかと思われます。
あるいは、「客にタダで遊ばれて満足されたら困る」からと、もしかしたらオペレーターからのクレームがあったのかもしれません。
以上、「デモ画面」の例をいろいろとご覧いただきましたが、どんなご感想をお持ちになったでしょうか?
今回ご紹介したタイトル以外にも、現在のゲームセンターでは『NESiCAxLive2(ネシカクロスライブツー)』や『ALL.Net P-ras MULTI(オールネットプラスマルチ)』など、ネットワークを介して新しく配信されたソフトを追加できるシステム基板が稼働しています。
これらの基板は、1枚(1台)でたくさんのタイトルが遊べるのがメリットで、遊べるタイトルを十数秒ごとにローテーション方式で「デモ画面」を流しています。
ですが、タイトルによっては途中でプレイデモが途切れてしまったり、ただアニメーションを流すだけで終わってしまうため、傍目には何をして遊ぶゲームなのかが全然わからないことがあります。
また、プレイデモ中の動画が実際のゲーム画面ではなく、別に用意された動画ファイルを再生しているため、実際のゲーム画面より画質が劣り、かえって見栄えを悪くしているケースがあるのも筆者は気になっています。
すでに「消えた文化」になりかかっている感もありますが、個々のタイトルや時代に即した「デモ画面」の演出は、まだまだ研究、工夫の余地があるように思われます。
なお、「デモ画面」に関するくわしい説明は、サイトウ先生と筆者の共著「ビジネスを変える『ゲームニクス』」の「原則2-B-③:デモでルールを説明する」のところに書かれていますので、ご興味のある方はぜひご一読ください。
それでは、また次回!